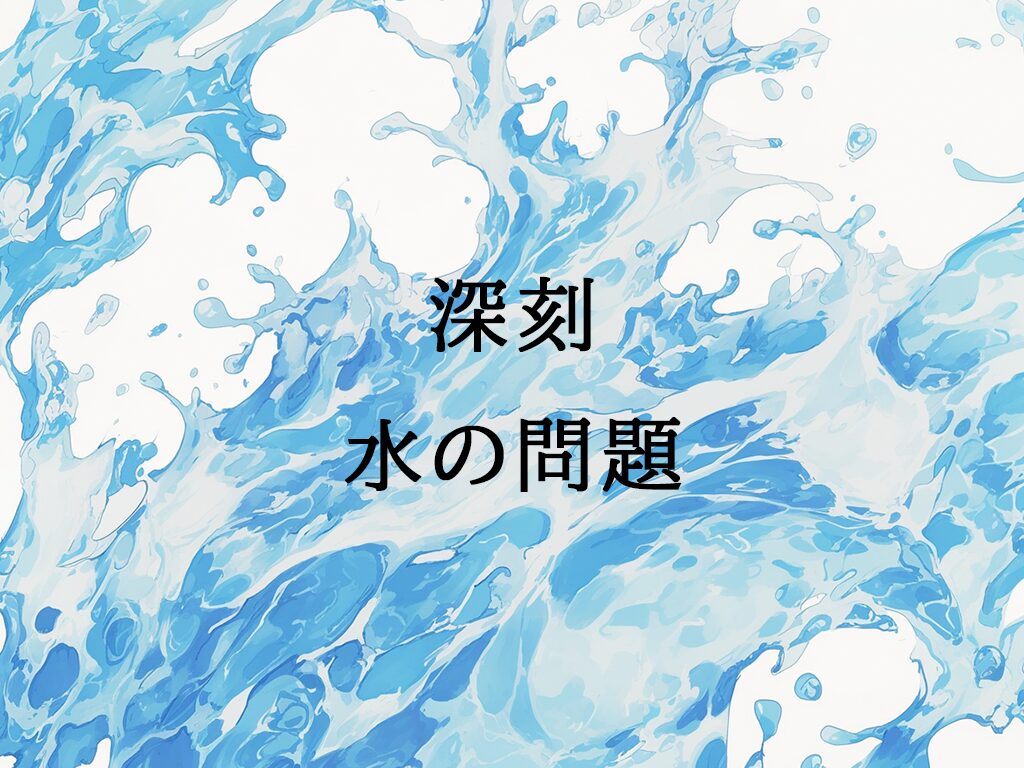地球上において、水は生命に不可欠な資源です。
地球の表面積の約70%が水に覆われており、その豊富さから「水の惑星」とも呼ばれることがありますが、そのほとんどが人間の生活には使えない海水であり、淡水はわずか2.5%しか存在しません。
さらに、私たち人類が実際に利用できる水資源は、地球全体の水のうち実はたったの0.01%に過ぎないのです。
そして、今世界では人口の増加や気候変動などが原因で、水の需要は急激に増加しています。
途上国などでは清潔で安全な水を手に入れることが難しく、多くの人々が水不足や不衛生な水に苦しんでいます。
日本に住む私たちは蛇口をひねれば飲める水が出てくる生活に慣れていますが、世界の多くの地域では、日々の水の確保さえ生命を大きく左右する問題です。
今回は、世界と日本が抱える水の問題について深く掘り下げていきます。
水の持続可能な利用を実現するために、私たちが何を知り、どのような行動を起こすべきかを考える機会となれば嬉しいです。
世界が抱える水の問題
水不足と水資源の分布
地球には海、川、湖、地下水など、多様な形で水が存在していますが、その97.5%は海水です。
淡水はわずか2.5%しかなく、さらにその多くは南極や北極の氷河、永久凍土として存在しているため、私たちが直接利用できる水は限られています。
実際に利用可能な淡水は地球全体の水のうちたったの0.01%に過ぎないという事実は、水不足が決して途上国に限らず、全世界的な課題であることを示しています。
この限られた水資源の分布により、各地で慢性的な水不足が発生しています。
アフリカや中東など、乾燥した気候の地域では特に深刻で、こうした地域では生活用水を確保するために遠くまで歩き、水汲みをしなければならないことが日常化しています。
人間にとって必要不可欠な「水の不足」は、生活に直結する切実な問題なのです。

安全な飲み水の不足
水の安全性もまた、世界の重要な課題です。
世界保健機関(WHO)の調査によると、現在、世界には約22億人もの人々が安全に管理された飲み水を利用できない環境に置かれています。
これは、地表の川や湖、または未処理の水を生活用水として利用している人々が多いことを意味します。こうした状況では、細菌や寄生虫が混入した不衛生な水を使用せざるを得ないため、深刻な健康被害が発生しています。
抵抗力の弱い子どもたちにとってこの問題は死活問題です。
例えば、不衛生な水によって下痢を引き起こし、それが原因で毎日900人以上の5歳未満の子どもが命を落としているといわれています。
これは、安全な水へのアクセスが健康や生存に与える影響の大きさを如実に表していると言えますよね。
水質汚染と衛生設備の不足
水道やトイレ、下水設備が整備されていない地域では、生活排水がそのまま近くの川や湖に流れ込み、飲用水が汚染される事態が頻発しています。
インドネシアのチタルム川は「世界で最も汚染された川」と称され、鉛や有害化学物質が基準値の数百倍以上含まれていることが確認されています。それでも多くの住民は、やむを得ずこの水を生活用水として使っているのが現状です。
こうした地域では、水汲みや排泄が生活の一部であるために衛生環境の確保が難しく、不衛生な生活が健康リスクを増大させます。
衛生設備の整備は単に水の安全性を確保するだけでなく、住民の健康と生活の質を大きく改善するために不可欠なのです。
水ストレスとその指標
「水ストレス」とは、1人当たりの年間利用可能水量が1,700立方メートルを下回る状態を指します。さらにこの値が1,000立方メートルを下回ると「水不足」、500立方メートル以下になると「絶対的な水不足」と定義されます。
サハラ以南アフリカ、南アジア、中東などは水ストレスが非常に高い地域であり、各国で深刻な水不足が発生しています。
特に乾燥地域では水の需要が高まり、わずかな水資源をめぐって紛争が発生することも少なくありません。
地球上の人口が増加する中で、限られた水資源をどう確保するかは大きな課題であり、解決には国際的な協力が求められます。
人口増加と産業発展の影響
世界の人口は増加の一途をたどり、2050年には約97億人に達すると予測されています。この急激な人口増加は、水の需要をさらに押し上げ、生活用水や農業・工業の水使用量が増大することが懸念されています。
実際、農業用水が水の全消費量の70%を占めており、工業用水の需要も増え続けています。産業の発展による水質汚染も進行しているので、適切な管理が行われなければ使用可能な水資源はより一層減少していくと考えられています。
気候変動と自然災害の影響
干ばつや洪水が頻発し、特に水資源が乏しい地域では深刻な影響が生じています。
気温上昇による雪解けの加速や積雪量の減少は、河川の水量にも影響を及ぼし、結果的に飲料水や農業用水の不足を引き起こす要因ともなっています。
気候変動によって砂漠化が進行し、利用可能な水資源がさらに減少するリスクも高まっています。
こうした自然災害の増加は、単に物理的な水不足だけでなく食料生産や生態系への影響も引き起こすため、幅広い分野での影響が懸念されます。

水をめぐる紛争と対立
水資源をめぐる対立や紛争も、世界の水問題の一端です。
国際河川であるナイル川やインダス川では、上流と下流の国々の間で水の利用や配分を巡る争いが絶えません。例えば、エチオピアが建設中のダムに対して、下流に位置するエジプトとスーダンが懸念を示し、国際的な対立に発展した事例があります。
水不足が引き起こす紛争は、単なる資源争奪の問題ではありません。
水インフラが破壊されることで住民の生活が脅かされ、地域の安定を損なう要因となるのです。限られた水をどう公平に分配するかは、今後も国際社会が取り組むべき重要課題でしょう。
日本が抱える水の問題
都市化と水循環の課題
日本の急速な都市化は、水循環に大きな影響を及ぼしています。
都市部では道路や建物が密集し、地表がコンクリートで覆われているため、降水が地下に浸透しにくくなっています。
本来であれば森林や土壌が雨水を吸収し、地下水を蓄えつつゆっくりと流域に供給することで水循環が保たれます。しかし都市化によってこのプロセスが阻害され、地下水涵養が困難になっています。地下水位が低下することで湧水が減少し、さらには渇水や都市型洪水のリスクが高まることが懸念されています。
「地下水涵養(ちかすいかんよう)」とは、雨水や河川水が地面に浸透し、地下水として蓄えられるプロセスを指します。自然の土壌や森林はスポンジのように水を吸収し、ゆっくりと地下へ送り込む役割を果たしています。これにより、地下水は安定的に供給され、川の水量や湧水の維持に寄与します。都市化が進むと、地表がコンクリートで覆われ、地下水涵養が妨げられ、地下水位の低下や渇水のリスクが高まることが懸念されています。
具体例として、首都圏では豪雨のたびに地下水の涵養が追いつかず、道路が冠水したり、下水道が処理しきれなくなったりといった都市型水害が発生しています。
都市化の進む東京都では集中豪雨時に地下に浸透しない雨水が一気に流れ出し、川の氾濫や浸水被害を引き起こしています。こうした都市型水害は、全国の都市部で共通する課題となっています。
さらに、コンクリートで覆われた都市部では、強い雨が降ると水が地中に浸透せず、地表を流れ川に流れ込みやすくなり、その結果として洪水リスクが増大します。都市化が進む中で、地元自治体や住民はこうした水害リスクへの備えを一層強化する必要に迫られています。

老朽化した水インフラ
日本の水インフラの多くは、1960〜1970年代の高度経済成長期に整備されたもので、老朽化が深刻化しています。
上下水道の配管や浄水場などは、当時の急増する人口と産業需要に対応するために急速に建設されましたが、その結果として、メンテナンスや更新の必要性が増大しています。
自然災害が多発する日本では、こうした老朽インフラの耐震性が低下しており、災害時に水供給が途絶えるリスクが高まっていることが指摘されています。
例えば、2011年の東日本大震災では、被災地の水道施設が広範囲で破損し、多くの地域で数週間から数か月にわたって水の供給が止まりました。このような災害によってもたらされる水インフラの脆弱性は、今後の復旧や維持管理のあり方を再検討する契機となりました。
さらに、インフラの老朽化が進む一方で、更新に必要な人材や資金の確保が難しいという問題もあります。
地方自治体においては、人口減少や高齢化の影響で財政が厳しく、インフラのメンテナンスに十分な予算が割けない状況が続いています。このままでは、今後も自然災害による大規模な水道施設の破損リスクが増大する可能性があるため、持続可能な水供給のための対策が急務とされています。
森林減少による水源涵養機能の低下
日本の水資源を支える重要な要素の一つが森林です。
森林は雨水を蓄え、少しずつ地下水に浸透させることで、河川や湧水の水量を安定させる役割を担っています。しかし、都市化や農業の放棄地が増えることで、森林面積が徐々に減少しており、水源涵養機能が低下しています。
また、森林伐採だけでなく、管理が行き届かない放棄された農地も問題です。
こうした土地は、土壌が劣化しやすく、雨水が効果的に蓄えられなくなるため、洪水や土砂崩れのリスクも増大します。
日本国内では地域によっては、山間部の過疎化や高齢化により、森林の管理が難しくなっている地域も多く、これが水源地の劣化につながっています。
例えば、熊本県や高知県の流域地域では、地元住民や自治体が連携し、地下水や河川の保全活動を実施しています。これにより、地域の水資源を守る取り組みが進められていますが、全国的な規模での対策が必要であることは言うまでもありません。
日本においても、水源涵養機能の維持と森林の保護は持続可能な水利用のために欠かせない課題です。
バーチャルウォーター(仮想水)の消費
日本が抱える水問題には、国内だけでなく国外の水資源を間接的に消費する「バーチャルウォーター」の問題もあります。
バーチャルウォーターとは、輸入された食料や製品の生産に必要とされた水のことですが、日本は多くの食料を輸入しているため、他国の水資源を間接的に利用している状態のことを指しています。
例えば、牛肉1キログラムの生産には約20,000リットルもの水が必要とされていますが、日本が海外から牛肉を輸入することは膨大な量の水を消費することに等しいと考えられます。
輸入食品の消費が進む日本は、国際的な水資源利用に依存する形になっており、他国の水問題にも無関心ではいられません。
バーチャルウォーターの視点からも、日本が持続可能な水資源の利用を模索することは国際社会における責務といえるでしょう。食品や製品を選択する際に、水の消費量も意識することが、未来の水資源保全につながるといえます。

気候変動と日本の水災害リスク
日本では集中豪雨の発生頻度が増加しており、大雨による河川の氾濫や土砂災害が頻発しています。
2018年の西日本豪雨や、2020年の九州豪雨などがその典型で、こうした水害は都市部でも河川の氾濫や住宅地の浸水を引き起こし、甚大な被害をもたらしました。
また、気候変動により冬季の積雪が減少し、春から夏にかけての河川水量が減少する傾向も見られています。これにより、一部地域では渇水のリスクも増大しています。
降水量が不規則になると、農業や工業の用水にも影響を及ぼし、社会全体で水の安定供給が課題となります。
こうした水災害リスクを減少させるためには、地域ごとの水資源管理や洪水対策が必要です。
全国的に水の利用を効率化し、災害発生時に備えるための持続的な水利用システムを確立することが求められています。日本は災害大国であるからこそ、気候変動に伴う水災害リスクに対して積極的な対策を講じることが不可欠です。
世界と日本の水問題解決に向けた取り組み
SDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」
持続可能な開発目標(SDGs)は、国連が2015年に採択した2030年までの17の目標群であり、各国が協力して地球規模の課題解決を目指すものです。
その中で、水問題に特化した目標として設定されたのが「目標6:安全な水とトイレを世界中に」です。この目標の達成は、特に安全な飲み水や衛生的な環境が確保できていない途上国の人々にとって、健康的な生活への第一歩とされています。
こちらも合わせてお読みください
目標6はさらに8つの具体的なターゲットに分かれており、それぞれが達成すべき具体的な基準を示しています。
例えば、6.1「2030年までに安全で安価な飲料水への普遍的かつ衡平なアクセスを達成する」、6.3「水質の改善、汚染物の削減、安全な再利用の促進」などが挙げられます。
国際NGOやユニセフの活動
国際社会における水問題解決の取り組みの中で、NGOや国際機関の活動は欠かせません。
国連児童基金(ユニセフ)では、水と衛生に関する支援を通じて、途上国の子どもたちの健康改善に取り組んでいます。ユニセフの活動は、井戸の設置やトイレの普及を通じて安全な水を供給するだけでなく、衛生教育を通じて清潔な生活習慣の普及も図っています。これにより、子どもたちが安全な水を得られ、健康に育つための基盤が整えられています。
ワールド・ビジョンなどの国際NGOも、地域社会が持続可能な水管理を行えるよう、住民への技術支援や教育を提供しています。
インドやアフリカの村落で浄水設備を整備するプロジェクトや、学校で手洗いの習慣を広める啓発活動が行われています。これにより、子どもたちが衛生知識を身につけ、健康を守ることが可能になるのです。
日本のODAと技術支援
日本は水問題の解決に向け、政府開発援助(ODA)を通じて国際的な貢献を果たしています。
日本のODAは、特に水インフラ整備や技術支援において顕著であり、発展途上国の水道整備や水質改善、衛生設備の提供など、多岐にわたる支援が行われています。
具体例としては、日本はアジアやアフリカの国々で上下水道の整備や浄水施設の設置を支援しています。
技術支援では、現地の技術者に日本の浄水技術を伝えるための研修プログラムが実施されており、これによって現地での技術移転が進められています。また、日本のODAでは災害リスク軽減に向けた水防災対策も重視されており、自然災害の多い地域での洪水対策や渇水対策に力を入れています。
日本企業の海水淡水化技術と最新テクノロジー
日本の企業は、世界的に評価の高い水処理技術を提供しており、特にRO膜を使った海水淡水化技術ではトップレベルです。
RO膜(逆浸透膜)技術は、海水から塩分を除去して飲用可能な淡水に変える技術であり、水不足が深刻な地域での解決策として大きな期待が寄せられています。
RO膜(逆浸透膜)技術は、水中の不純物や塩分を除去するための高度な水処理技術です。「逆浸透膜(Reverse Osmosis membrane)」とは、非常に微細な孔を持つ特殊な膜で、海水や汚染された水を高圧で押し通すことで、塩分や微生物、有害物質などを取り除きます。これにより、飲料水や工業用水として利用可能な純水が得られます。この技術は特に海水淡水化プラントや工業排水の再利用に役立ち、水資源が限られた地域で注目されています。
この技術はシンガポールや中東地域など水資源の乏しい国々において、飲料水の安定供給に貢献しています。
例えば日本企業の東レは、シンガポールの海水淡水化プラントにRO膜技術を提供しており、現地の水供給を支えています。RO膜による淡水化技術は、省エネや低コスト化も進められており、さらなる普及が期待される分野です。
地域ごとの取り組みと啓発活動
熊本市では、地域の地下水を守るために、住民と行政が協力して地下水保全活動を行っています。熊本市では地下水が主要な水源となっているため、地下水位の管理や水田の保全活動が推進されており、持続可能な水利用を目指しています。
福井県の大野市では地域の湧水文化を守る活動が盛んであり、住民が「水のがっこう」を通じて水の大切さを学び、地下水の保全に取り組んでいます。
岡崎市(愛知県)でも、森林と水資源の保全活動が進められており、地域の自然と水循環の重要性を学ぶための自然体験プログラムが提供されています。
まとめ
水問題は単に途上国や遠い他国の問題ではなく、日本国内でも深刻化しつつある課題であることは間違いありません。
持続可能な水資源の利用を実現するために、私たちができることは何かを考えることが求められています。
日常的に節水を心がけることや、バーチャルウォーターの概念に注目し、消費行動における水の利用を意識することが挙げられます。
私たち一人ひとりが小さな行動を積み重ねることで、水問題解決に向けた大きな変化をもたらすことができるはずです。
国際社会や地域社会、そして私たち個人が協力して持続可能な水の未来を築くために、今後も意識を高め、行動を起こしていくことが必要です。