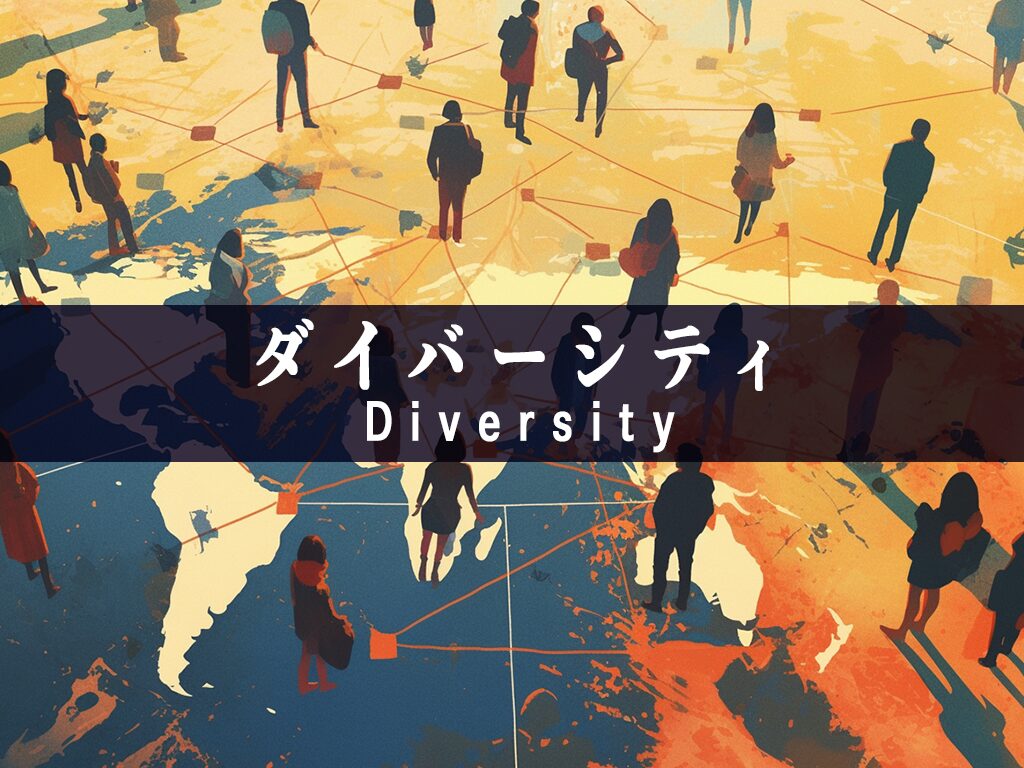「多様性」という言葉を耳にする機会が増えてきました。企業のホームページや求人情報、ニュースの見出しにも、当たり前のように登場します。けれど、その中身について本当に理解している人はどれだけいるでしょうか?
社会には今、「多様性の波」が確実に押し寄せています。
働き方改革やDXの加速により、労働の価値観は大きく変わりつつあります。加えて、日本が直面しているのは、少子高齢化と人口オーナス期という構造的課題。
厚生労働省によれば、2040年には労働力人口が約5,000万人を割り込むと予測されています。人手不足は、もはや一部業種の問題ではありません。あらゆる企業が、「誰に、どのように働いてもらうか」を真剣に考える時代に突入しているのです。
しかし、ダイバーシティは「人手を補うための戦略」だけではありません。むしろ真価はそこから先。異なる背景や価値観をもつ人たちが出会い、対話し、共に働くことによって、これまでにない発想や視点が生まれます。つまり、ダイバーシティは「課題への対処策」ではなく、「未来をつくる投資」なのです。
とはいえ、「多様性=良いこと」と単純に語るだけでは足りません。
多様性があるからこそ、すれ違いや誤解も生じます。文化的な違い、性別や年齢による固定観念、育ってきた価値観の衝突。ときに対立も避けられません。本当のダイバーシティは、違いを許容することだけでなく、その違いを「力」に変えていくプロセスにこそ価値があります。
だからこそ今、私たち一人ひとりが「ダイバーシティを知っている」から「ダイバーシティを実践する」存在へと、変わる必要があるのではないでしょうか。
目次
第1章:ダイバーシティとは?—言葉だけで終わらせない「多様性」の定義と価値
◆ビジネスにおける「ダイバーシティ」の定義
「ダイバーシティ(Diversity)」は直訳すれば「多様性」。しかし、ビジネスの現場で語られるこの言葉は単なる「違いの存在」を意味するものではありません。
企業が取り組むべきダイバーシティとは、「性別・年齢・国籍・価値観・経験などが異なる人材を積極的に受け入れ、その力を最大限に活かす経営のアプローチ」です。
たとえば日本企業では、同質性の高い組織が長らく続いてきましたが、現在では海外人材の登用、女性管理職の育成、LGBTQへの理解促進などを含め、多様性を前提とした組織改革が進められています。
そしてこの変化の背景には、「多様性が企業の成長力を高める」という明確な根拠があります。世界経済フォーラムによれば、多様性に富んだ企業のほうがそうでない企業よりも、イノベーションを生み出す確率が1.7倍高いというデータもあるほどです。
◆表層的 vs 深層的ダイバーシティ
多様性には「見える違い」と「見えない違い」の2つがあります。
前者は、性別・年齢・国籍・人種・障害の有無など、外見や戸籍情報などでわかる「表層的なダイバーシティ」。後者は、価値観・性格・育った環境・宗教観・人生経験・スキルといった「深層的なダイバーシティ」です。
社会はつい、見えやすい違いばかりを重視しがちです。しかし、実際にチームの力を高めたり、新しい価値を生み出したりするのは、深層的なダイバーシティの融合から生まれることが多いのです。
いわば、「見えない多様性こそが、組織の潜在力を引き出す鍵」とも言えるでしょう。
◆インクルージョンとエクイティ——“受け入れる”その先へ
ダイバーシティが「多様な人材を持つこと」ならば、インクルージョン(Inclusion)は「それぞれが対等に活躍できる状態をつくること」。つまり、ダイバーシティが“結果”であるのに対し、インクルージョンは“プロセス”です。
インクルージョンが成立している組織では、少数派の意見が無視されることなく、むしろ積極的に取り入れられます。会議で声の大きい人だけが評価されるような職場では、本当の多様性は機能しません。
そこにもうひとつ大切な視点が加わります。それが「エクイティ(Equity)」=公平性です。
「すべての人に平等なルールを」という考え方だけでは、スタートラインの差を無視することになります。たとえば、障害のある人に健常者と同じ職場環境を用意するだけでは、本当の意味で“公平”とは言えません。
個々人が持つ制約や背景に目を向け、それに応じた支援や機会を提供すること——それがエクイティの本質です。
◆DE&Iの視点で考える、組織と社会の理想像
近年では、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)にエクイティを加えた「DE&I」がスタンダードになりつつあります。
これは単なる流行ではありません。社会の根本的な価値観を見直すムーブメントです。
「違いを排除するのではなく、力として活かす」 「公平な土台のうえで、すべての人が尊重される」
この視点が組織に根付けば、企業文化が変わり、イノベーションが生まれ、結果的に競争力も高まります。そして、そうした変化の積み重ねが、より包摂的な社会の実現へとつながっていくのです。

第2章:なぜ今、ダイバーシティが求められているのか?
—背景にある社会課題と時代の変化
◆少子高齢化と人口オーナス期という現実
日本の人口構造は、かつてないスピードで変化しています。総務省統計局のデータによれば、2022年時点で65歳以上の高齢者は人口の29.1%を占め、世界でもトップクラスの高齢社会に突入しました。
同時に、15〜64歳の生産年齢人口は減少の一途をたどっています。この状態は「人口オーナス期」と呼ばれ、経済を支える現役世代が減り、社会保障や医療などの支出が増える“負担の時代”を意味します。
この人口構造の変化は、企業活動にも直結します。採用が難しくなり、働ける人材が限られるなかで、従来の「一括採用・終身雇用」モデルでは、企業の持続可能性すら危うくなります。
そこで求められるのが、ダイバーシティの視点です。性別や年齢にかかわらず、外国人や障害のある人、高齢者、育児や介護との両立が必要な人など、あらゆる人の「働ける可能性」を広げていくこと。これはもはや倫理の問題ではなく、企業にとっての“生存戦略”といえます。
◆SNSと価値観の多様化が生む“市場の複雑化”
情報が溢れる現代において、消費者の価値観は一枚岩ではなくなっています。SNSやYouTubeなどの発信プラットフォームが個人の声を可視化し、購買行動にも直接影響を与えるようになりました。
たとえば「環境に配慮した商品が欲しい」「女性が作ったプロダクトを応援したい」といった価値観は、少数派であっても声として可視化され、企業にプレッシャーをかけます。
企業側が画一的な視点にとどまっていては、こうした多様な市場ニーズに応えることは困難です。だからこそ、マーケティングや商品開発チームの中に、異なる視点を持つ人材がいることが重要になります。
多様性は「社内の声を市場に近づけるフィルター」であり、それ自体が競争優位性を生む時代が到来しているのです。
◆ワークライフバランスから“インテグレーション”へ
かつては「仕事」と「生活」をいかに分けるかが課題でしたが、今ではその境界自体が溶けつつあります。テレワークや副業制度の普及により、自宅で子どもを見ながら会議に出る、新幹線移動中に企画書を仕上げる、という働き方も当たり前になりました。
これに伴い、注目されているのが「ワークライフインテグレーション」という考え方です。これは仕事と生活を切り分けるのではなく、「統合的にデザインする」アプローチ。時間管理ではなく、人生全体の充実をどう設計するかが問われています。
ダイバーシティの実現には、こうした柔軟な働き方へのシフトも不可欠です。従来型の一律な制度設計では、多様な人が安心して働き続けることはできません。
◆イノベーション創出のための“異質性”の重要性
新しい価値を生み出すには、同じような考え方を持つ人の集団では限界があります。異なる文化や経験を持つ人が交わることで、これまでにない視点が生まれ、そこからイノベーションが芽吹くのです。
経済産業省の「人材版伊藤レポート2.0」では、非連続的なイノベーションの源泉として「知・経験のダイバーシティ」が明記されています。実際に、ボストンコンサルティンググループの調査では、経営陣に多様性のある企業はそうでない企業に比べて、イノベーション収益が19%高いという結果も出ています。
つまり、ダイバーシティは単なる倫理的価値ではなく、「新しい時代を切り拓くためのエンジン」なのです。

第3章:日本の「いま」を知る
—ダイバーシティの現状と課題
◆女性活躍の進展と限界(例:役員比率、制度ギャップ)
日本では、2016年に施行された「女性活躍推進法」により、多くの企業が女性管理職の比率を高めようと努力してきました。けれど実際の数字を見てみると、その進捗には限界も見られます。
たとえば、2022年時点での上場企業における女性役員の割合はわずか8.4%。政府が掲げた2020年までに10%という目標すら未達成です。制度は整いつつあっても、文化的・意識的な壁がいまだ根強いのが現状です。
また、育休後の復職支援や時短勤務制度が整備されていても、昇進や評価への影響を心配して制度の利用をためらう女性も多くいます。「制度はあるけれど、使いづらい」という声が現場からは聞こえてきます。
◆中小企業における推進格差と“やり方が分からない”という壁
大手企業ではダイバーシティの推進が進んでいる一方で、中小企業ではまだまだ導入が進んでいません。
パーソルホールディングスの調査によれば、中小企業において「十分に取り組めている」と回答した割合は30%未満。多くの経営者が「そもそも何から始めれば良いかわからない」「推進担当者がいない」という悩みを抱えています。
こうしたギャップは、情報格差やリソース不足が要因になっており、ダイバーシティを“余裕がある企業だけがやるもの”と誤解されがちです。
中小企業にこそ必要なのは、明確なガイドラインと小さく始められる支援策。そこで注目されているのが、経済産業省による「ダイバーシティ・コンパス」などの支援ツールです。
◆表面的な取り組みと、本質的な変化のズレ
名刺に「ダイバーシティ推進室」と書かれていても、社内の空気は何も変わっていない。そんなケースも少なくありません。
制度導入やイベント開催といった“見える取り組み”に力を入れる企業は多いですが、それが従業員の意識や行動に結びついていなければ、効果は限定的です。
たとえば、LGBTQ研修を一度受けたとしても、日常の会話に無意識の偏見があれば、それは“見かけ倒し”の取り組みにすぎません。
本質的な変化とは、個人の意識レベルで「多様性を尊重する姿勢」が自然と根づくこと。そのためには、トップダウンとボトムアップの両面からの働きかけが必要です。
◆政府の施策と制度支援(ダイバーシティ2.0、なでしこ銘柄 等)
政府もダイバーシティ推進に本腰を入れています。代表的なのが、経済産業省による「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」。これは企業が取り組むべき7つのアクションを提示し、ダイバーシティを経営戦略に統合することの重要性を明文化したものです。
その一環として、優れた取り組みを行う企業を「新・ダイバーシティ経営企業100選」や「なでしこ銘柄」として表彰する制度も展開。これにより、好事例を共有しながら業界全体への波及を狙っています。
こうした制度は、企業にとってダイバーシティを「ブランディング戦略」として捉える後押しにもなっており、今後の加速が期待される分野といえるでしょう。

第4章:企業が進むべき未来とは?
—戦略としてのダイバーシティ経営
◆経済産業省「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」とは?
企業がダイバーシティに取り組む意義は、もはや“CSR(社会貢献)”にとどまりません。いま注目されているのが「戦略としてのダイバーシティ経営」です。その象徴が、経済産業省が発表した「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」。
このガイドラインでは、ダイバーシティを「多様な人材の能力を最大限引き出し、付加価値を継続的に生み出す経営上の取組」と定義。単なる雇用機会の拡大ではなく、企業の競争力強化を目的とした“経営のアップデート”であることが明確に打ち出されています。
背景には、投資家や顧客が「多様性を尊重する企業」を評価する潮流があるからです。ESG投資や人的資本開示といったキーワードとも密接に関連しており、もはや「取り組まない企業がリスクを抱える」時代に移行しています。
◆実践の7つのアクション(経営戦略、環境整備、情報開示など)
このガイドラインが特筆すべきなのは、「実践のための7つのアクション」を明確に提示している点です。抽象的な理念ではなく、企業が“何をすれば良いのか”を具体的に指し示しています。
- 経営戦略への組み込み
経営トップがダイバーシティを経営戦略に不可欠と位置づけ、KPIやロードマップを策定。トップ自らが責任を持って推進。 - 推進体制の構築
経営幹部や事業部門を巻き込み、全社的な推進体制を整備。 - ガバナンスの改革
取締役会において、性別や国籍などの多様性を確保し、ダイバーシティ経営を監督。 - 全社的な環境・ルールの整備
働き方改革や柔軟な制度整備により、多様な人材が活躍できる土壌をつくる。 - 管理職の意識・行動改革
マネジメント層に対し、無意識バイアスを解消し、多様性を活かす能力を育成。 - 従業員の行動・意識改革
多様なキャリアパスを提示し、自律的なキャリア形成を支援。 - 情報開示と対話の推進
取り組みの内容と成果を、投資家や社会に向けて積極的に発信。
これらのアクションは、ただ理念を掲げるのではなく、「ダイバーシティを実際に成果に結びつける」ための実務的な道しるべになっています。
◆KPIとロードマップで“見える化”する組織の変革
変革を成功させるためには、「見える化」が欠かせません。
多くの企業が、「女性管理職比率を◯年までに30%」など、数値目標(KPI)を設定し、そこへ至るまでのステップをロードマップに落とし込んでいます。
たとえば、ある大手企業は、3年間で女性役員を2倍に増やす目標を掲げ、社内人材育成プログラムの強化と社外人材の積極採用を組み合わせて成果を出しました。
KPIは進捗状況を可視化し、社内外への説明責任を果たすうえでも有効です。数値は嘘をつきません。だからこそ、「言って終わり」ではなく、「結果を問う」姿勢が求められます。
◆人的資本経営と「知・経験の多様性」の融合
現在、世界的に注目されているのが「人的資本経営」。企業の価値は「人」で決まるという考え方に基づき、人材の質や多様性が企業評価の指標となっています。
なかでも注目されるのが、「知と経験のダイバーシティ」。これは、単に性別や国籍が異なるだけでなく、「異なる業界経験」「ユニークなスキル」「多様な思考スタイル」など、より深いレイヤーの違いを取り込む視点です。
異質な知識や視点のぶつかり合いからこそ、非連続的なイノベーションが生まれます。経営の中枢に、こうした知の多様性を取り込むことで、組織は変化に強くなり、未来への舵取りがしやすくなるのです。
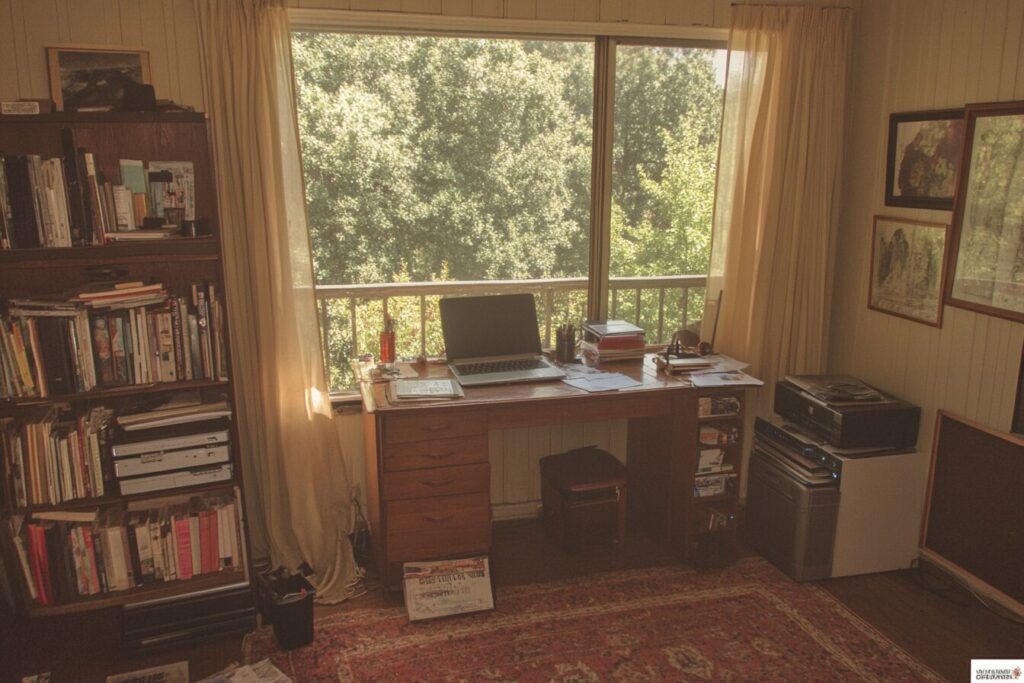
第5章:私たち個人にできること
—バイアスに気づき、社会を変える一歩を
◆無意識バイアスと向き合うことの大切さ
「自分は差別なんてしていない」——そう思っていても、無意識のうちに誰かをラベリングしてしまうことは誰にでもあります。
たとえば、「女性だから会議に参加しにくいのでは?」「障害があるから難しいかも」そんな“前提”がふとした言動に滲み出る。それが無意識バイアスです。
このバイアスに気づくことが、ダイバーシティを実践する最初の一歩。まずは「自分にも偏見があるかもしれない」と認めるところから始めましょう。
◆職場や日常でできる、実践的なインクルージョン行動
特別なことをする必要はありません。身近なところに、できることはたくさんあります。
・会議で発言が少ない人に「どう思う?」と声をかけてみる
・多様な視点に触れるため、異なる背景を持つ人と雑談してみる
・意見が衝突したとき、「違う」ではなく「違っていい」と受け止める
こうした行動の積み重ねが、インクルーシブな文化を育てます。制度ではなく、“関わり方”が職場の空気を変えるのです。
◆情報を選ぶ、伝える、学び続ける
情報との向き合い方も重要です。SNSやニュースで目にする話題に対して、「これは偏った見方かもしれない」と立ち止まって考える習慣をつけてみてください。
本を読んだり、ポッドキャストを聞いたり、異文化に触れる映画を観ることも、学びの一つ。意識的に“違う世界”に触れることで、視野が広がっていきます。
知識は人を変えます。そして、その人が職場や家庭で周囲に影響を与えていく。変化は、一人から始まるのです。
◆ダイバーシティを「寄付」や「支援」で応援するという選択肢
行動する力は、必ずしも声を上げることだけではありません。
社会的に弱い立場にある人々や、ダイバーシティ推進に取り組むNPO・団体に「寄付をする」「ボランティアとして関わる」などの支援も、大切な一歩です。
たとえば、LGBTQ支援、障害者の就労支援、外国人の教育支援など、多くの団体が現場で奮闘しています。時間がなくても、ワンクリックでできる寄付やSNSでの情報シェアなど、小さな行動が大きな変化につながります。
自分にできる方法で、社会に関わっていく——その姿勢こそが、ダイバーシティを育てる力になります。

最終章:目指すべき社会
—誰もが「その人らしく」いられる未来へ
◆多様性が競争力と創造性を生む社会
時代の変化は、もはや待ってくれません。テクノロジー、価値観、ライフスタイル——あらゆるものが流動化する現代において、企業や組織が生き残るために必要なのは「適応力」ではなく、「創造力」です。
その創造力の源となるのが、異なる視点の交錯。つまりダイバーシティなのです。
マッキンゼー・アンド・カンパニーの調査によれば、性別や人種などで多様性の高い企業は、財務パフォーマンスでも上位25%に入る確率が平均より最大36%も高いというデータがあります。
これは偶然ではなく、多様な価値観を組織に取り入れた結果として、意思決定の質が高まり、新しいアイデアが生まれ、リスク管理能力も強化された証拠です。
日本社会が直面している課題は、少子高齢化だけではありません。地政学リスク、気候危機、格差の拡大など、多方面に及びます。そのなかで「正解のない問い」に対して柔軟に答えを探す力が、これからの競争力になります。
その力を育てるのが、多様性であり、その活用方法を磨くのがインクルージョンなのです。
◆分断ではなく共生と補完の価値観
世界中で分断が深まっている今、私たちに必要なのは「違いを無くすこと」ではありません。「違いを補い合う関係」をどう築けるか、その姿勢です。
人はそれぞれ、得意なことも苦手なことも異なります。ある人はロジカルに物事を考えるのが得意かもしれないし、ある人は感情に寄り添う力に長けているかもしれません。
どちらが上でも下でもない。むしろそれぞれの特性が組み合わさることで、ひとつの強いチームが生まれます。
これは職場に限らず、地域や家庭、教育の現場でも同じことが言えます。高齢者と若者、外国にルーツを持つ人と日本で生まれ育った人。立場や文化、経験の違いはあれど、「お互いを活かし合える関係」が築ければ、社会はもっとしなやかで、強くなれるはずです。
違いは、恐れるものではなく、未来を豊かにする“資源”。共に生きるとは、同じになることではなく、それぞれが輝ける場所を認め合うことではないでしょうか。
◆一人ひとりの違いが尊重される、持続可能な社会づくり
国連が掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」にも、多様性や包摂性の重要性は繰り返し示されています。目標5(ジェンダー平等)、目標10(人や国の不平等をなくす)などは、まさに社会の仕組みそのものに「多様性を組み込む」ことを求めています。
持続可能な社会とは、環境だけでなく、人の尊厳と可能性が守られる社会でもあります。貧困や差別、孤立をなくし、誰もが社会の一員として役割を持てる社会。それが、真に持続可能な社会の姿です。
そしてその未来を実現するのは、国家や企業だけではありません。一人ひとりの「気づき」と「行動」が、社会を少しずつ動かしていく力になります。
職場で、学校で、家庭で。「あなたらしくいていいよ」と言える空気を、私たちがつくっていけたなら。
それは、違いを尊重するという“人間らしさ”を回復することでもあります。
私たちが目指すべき社会は、誰もが「その人らしく」生きていける場所。違いを隔てる壁ではなく、違いを活かす橋が架かっている未来を、一緒に育てていきましょう。