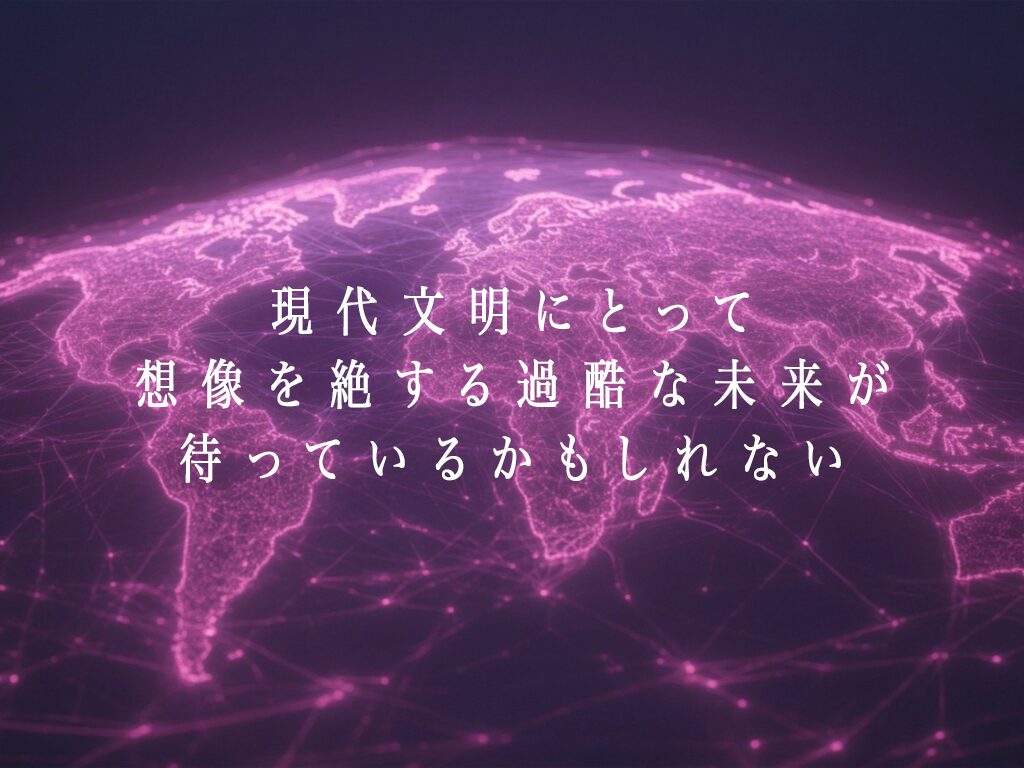気候変動によって異常気象が世界各地で頻発し、その被害が深刻化しています。
近年、地球の平均気温は産業革命前に比べて約1.1℃上昇しており、2015~2022年は観測史上もっとも暑い8年間となりました。
その結果、かつては稀だった極端な気象現象が各地で立て続けに起こり、「異常気象」がもはや異常ではない時代に入りつつあります。実際、豪雨による洪水や干ばつ、熱波などが毎年のように各大陸で発生し、その経済的損失も増大しています。
科学者たちは「人間の活動による気候変動が、すでに世界中のあらゆる地域の極端気象(熱波・豪雨・干ばつ・熱帯低気圧など)に影響を及ぼしている」と指摘しています。
本記事では、気候変動がもたらす異常気象の現状と将来リスクを、最新のデータや科学的知見に基づいて網羅的に解説します。被害の実態と予測を正しく理解することで、「異常気象時代」に備える手がかりとしましょう。
目次
進む地球温暖化と異常気象の現状
地球規模の温暖化に伴い、気温だけでなく降水や風など気候システム全体に広範な変化が現れています。そのスピードは人類社会が経験したことのない速さで、例えば海面上昇は1970年以降加速し、直近10年では年間約4ミリのペースに達しています。
こうした気候の変化により、極端な天候による災害リスクが高まっているのが現状です。
世界気象機関(WMO)の報告によれば、1970~2019年の50年間で気象・気候・水象災害の発生件数は5倍に増加し、経済的被害額は7倍にも拡大しました。
幸い、予警報の改善などで死亡者数は約3分の1に減少しましたが、被害を受ける人々の数は増えています。
実際、2022年には干ばつ・洪水・熱波が全大陸で発生し、数百億ドル規模の被害をもたらしました。今年に入ってからも、欧州やアジア、アフリカなど各地で気象災害が相次ぎ、被災者の救援が追いつかない事態も起きています。
では、具体的にどのような異常気象が増えているのでしょうか。
次からは、主な災害種別ごとに現状を見てみます。
水害:頻発する豪雨と洪水
異常気象の中でも近年顕著なのが、記録的な大雨による洪水被害です。大気が温暖化すると水蒸気保持量が増えて雨量が激化するため、世界各地で短時間の豪雨や集中豪雨が増加しています。
日本でも気象庁の分析で、1時間80ミリ以上や日降水量300ミリ以上といった非常に激しい雨の発生頻度が、1980年頃と比べ最近の10年間でおおむね2倍に増加していることが確認されています。
これは温暖化により大気中の水蒸気量が増え、かつ豪雨をもたらす積乱雲が発達しやすくなっているためと考えられています。実際、「数十年に一度」と言われるような雨量の記録更新が相次いでいます。
日本では2018年7月の西日本豪雨(平成30年7月豪雨)で各地の観測史上最大雨量を記録し、200名以上の尊い命が奪われました。その後も2020年の熊本豪雨や2019年の台風19号(東日本台風)による豪雨など、大規模な水害が毎年のように発生しています。
海外に目を向けると、2021年夏にはドイツやベルギーで記録的豪雨による河川氾濫が発生し、欧州で200人超が犠牲となる大惨事となりました。
さらに2022年にはパキスタンでモンスーンの集中豪雨が国土の3分の1を水没させ、約33万人が被災する未曾有の洪水が発生しています。
パキスタンでは8月の月間雨量が平年の7~8倍に達し、少なくとも1500人以上が死亡しました。このように、「観測史上例のない」雨量による洪水が各地で相次いでいるのです。
科学者たちは、気候変動がこれら豪雨・洪水災害に与える影響を分析しています。
欧州の豪雨災害では気候変動が極端降雨の発生確率を数倍程度高めたとの研究結果が報告されました。またパキスタン洪水についての国際研究では、人為的な気候変化によりモンスーン降雨が極端化し、同国のような脆弱な地域社会で被害を深刻化させた可能性が高いと指摘されています。
洪水リスクは沿岸部でも高まっており、高潮や高波による沿岸洪水の発生頻度は1960年代に比べて約2倍に増加しました。温暖化に伴う海面上昇と豪雨の増加が重なり、今後も水害リスクは一層高まると予想されています。

森林火災:広がる火災リスク
森林火災(山火事)もまた、気候変動によって被害が拡大している災害の一つです。
もともと森の火災自体は自然現象でもありますが、近年の火災は規模・頻度ともに異常なレベルに達しています。
地球全体で見ると、森林火災で失われる樹木の面積は20年前の約2倍にも及んでいます。
衛星データを解析した研究によれば、2001年頃と比べて毎年約700万エーカー(日本の四国ほどの面積)も多くの森林が火災で失われているとのことです。特に被害が大きいのはシベリアやカナダなど高緯度の森林地帯で、ロシアでは2021年に1300万エーカー以上(2001年の6倍超)の森林が焼失しました。
高緯度地域は地球平均より速いペースで温暖化が進行しており、それが火災の巨大化に拍車をかけていると考えられています。
気温上昇と降雨減少の組み合わせにより土地が乾燥し、火災の発生・延焼しやすい条件が整ってしまうのが主因です。長引く熱波や少雨が落雷や人為的要因で始まった火を「超大型火災」へと成長させ、コミュニティ全体を飲み込むケースが増えています。
たとえば2019~2020年のオーストラリアでは記録的な高温乾燥により広範囲で森林火災(いわゆる「ブラックサマー」)が発生し、1億匹以上の野生動物が死亡するなど生態系にも壊滅的な被害が出ました。
米国カリフォルニア州でも毎年のように過去最大規模の山火事が更新され、2020年には年間延焼面積が400万エーカー(東京都の約20倍)に達しています。研究によれば、1970年代以降の米西部の乾燥度上昇の主な原因は人為的な気候変動であり、それによって森林火災の焼失面積が2倍に拡大したことが示されています。
森林火災は単に燃える森林の面積だけでなく、人間社会への健康被害や経済損失も深刻化させています。
煙による大気汚染は遠く離れた都市の空気も汚染し、肺や心臓への健康リスクを高めます。さらに、森林が焼失すればそれだけ大量の二酸化炭素が大気中に放出されるため、気候変動そのものを加速させる「悪循環」にもなります。
実際、近年の大規模火災で放出されたCO2量は、一国の年間排出量に匹敵する場合もあります。こうした事態を防ぐには、気候変動の進行を食い止めるとともに、森林管理(間伐や防火帯の整備など)や早期消火体制の強化がますます重要になっています。

台風・ハリケーン:勢力の強まる嵐
海水温の上昇により、台風やハリケーンといった熱帯低気圧の勢力も強まる傾向が指摘されています。
統計上、温暖化に伴って全球的な熱帯低気圧の発生数そのものの顕著な増減は確認されていませんが、カテゴリー5に相当するような最高強度の嵐が増えている可能性があります。
気象庁の分析でも「強い台風」の発生割合が長期的に増加傾向を示しており、将来も風速・降水量ともに強まる予測が出されています。温暖化した海洋は膨大な熱エネルギーを台風に供給し、結果として猛烈な強風と豪雨を伴うスーパー台風が発達しやすくなるのです。
近年の事例を見ると、フィリピンを襲った台風ハイエン(2013年)は記録的な高潮で甚大な被害を出し、アメリカ・バハマに壊滅的打撃を与えたハリケーン・ドリアン(2019年)は最大風速が毎秒約85メートルに達しました。
また日本でも、2019年の台風19号(ハギビス)は「狩野川台風以来の暴風雨」と報じられ、記録的豪雨による堤防決壊が各地で起こっています。台風がもたらす総雨量も増える傾向にあり、ハリケーンや台風による豪雨災害リスクは高まっています。
例えばハリケーン・ハービー(2017年)はテキサス州に1,000ミリを超える猛烈な雨を降らせ、ヒューストン周辺で大洪水を引き起こしましたが、研究者らはこのような極端降雨現象が今後増えると警鐘を鳴らしています。
さらに、将来的には台風の移動速度の低下も懸念されています。
大気循環の変化により台風が同じ地域に長く留まれば、それだけ総雨量が増えて被害が拡大します(いわゆる「停滞台風」現象)。現在でも「50年に一度」の猛烈な勢力と言われる台風が毎年のように発生しつつあり、太平洋・大西洋の沿岸部では防潮堤の強化や早期避難体制など、気候変動を見据えた防災策が急務となっています。
熱波:記録的猛暑の頻発
酷暑や熱波もまた、気候変動が直接もたらす脅威です。
地球全体が温暖化する中で、夏季の極端な高温現象は格段に起こりやすくなっています。
日本では猛暑日(最高気温35℃以上)の発生が顕著に増えており、気象庁のデータによると近年の全国の猛暑日日数は1970年代と比べて約3倍にも増加しています。都市化の影響も一部ありますが、広域的な気温上昇により真夏日の期間が長期化し、夜間も気温が下がりにくい熱帯夜の増加も報告されています。このため、熱中症患者の数も年々増え、高齢者を中心に命に関わるケースが後を絶ちません。
世界的にも近年の猛暑は顕著で、各地で過去最高気温の記録が塗り替えられました。
例えばカナダでは2021年6月にブリティッシュコロンビア州リットンで摂氏49.6℃という驚異的な高温を観測し、数百人規模の熱死者が発生しました。
科学者による事後解析では、このような異常高温は人為的な気候変動がなければ「ほぼ起こり得なかった」とされています。
実際のところ現在の気温水準(産業革命前より+1.2℃程度)でも、観測史上前例のない熱波が各地で頻発しています。欧州でも2022年夏にイギリスで初めて40℃を超える猛暑日を記録し、フランスやスペインでも連日のように40℃台後半の猛烈な暑さとなりました。
これらの熱波によるヨーロッパの超過死亡は数万人規模と推計されており、熱波は現代で最も死者数の多い自然災害の一つになりつつあります。
将来、さらなる温暖化が進めば猛暑の深刻度は一段と増します。
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)によれば、全球平均気温の上昇が1.5℃にとどまった場合でも、極端な高温や長期間の熱波が増えると予測されますが、2℃上昇に達すると人の健康や農業にとって耐え難い猛暑が格段に頻発するとされています。
高温そのものによる健康被害だけでなく、干ばつや山火事の誘発、インフラへの損傷(鉄道のレールの歪みや送電設備のトラブルなど)といった波及効果も無視できません。
猛暑に備えて都市の緑化やクーラー設備、熱中症対策を進めると同時に、長期的には気候変動そのものを緩和しない限り根本的な解決にならない点で、非常に難しい課題です。

干ばつ:水不足と食糧危機への影響
反対に雨が極端に少ない干ばつ(旱魃)も、気候変動によって深刻化しています。
大気と陸地の温度が上がることで蒸発量が増加し、土壌の乾燥が進みやすくなるためです。その結果、降水量が平年並みでも土壌水分が不足して農作物が育たなかったり、少し雨が少ないだけで深刻な水不足に陥ったりする地域が出てきています。近年もっとも悲惨な干ばつ被害が発生した地域の一つがアフリカの東部(ホーン・アフリカ)です。
2020年頃から雨季の不順が続き、2020~2022年にかけて雨季が連続して大失敗した結果、40年ぶりとも言われる大干ばつとなりました。
作物不作や家畜の大量死、水資源の枯渇により住民は深刻な食糧危機に直面し、国境を越えた難民も発生しました。
この干ばつについての分析では、人為的気候変動がなければそもそもここまでの干ばつには至らなかった可能性が高く、現在の気候では同程度の干ばつが100倍も起こりやすくなっているとの報告があります。
特に高温による蒸発量の増加が干ばつを一層悪化させており、同地域では今後も気候変動に伴う降雨パターンの変化と相まって、水不足と洪水の両極端に備えた適応策が必要だと指摘されています。
干ばつはアフリカに限った話ではありません。ヨーロッパ南部も近年雨不足と高温の組み合わせで深刻な渇水に見舞われており、2022年夏にはフランスやイタリアで河川の水位低下や農作物の減収が大きな問題となりました。
中国でも長江流域で記録的干ばつが発生し、水力発電や工業生産に支障をきたしました。
アメリカ西部では過去数十年に及ぶ慢性的な乾燥傾向が続き、カリフォルニア州などでは巨大貯水池の水位が歴史的低水準に陥っています。研究によれば、西部の近年の乾燥は過去1200年で最悪レベルであり、その主因は人為起源の気候変化だとされています。将来、地中海性気候の地域や亜熱帯の一部では降水量の平均的な減少も予測されており、これら地域の干ばつリスクは一層増大するでしょう。
干ばつは人間の飲み水や農業用水を不足させるだけでなく、発電(特に水力)や工業プロセス、さらには生態系にも大きなダメージを与えます。
水不足が深刻化すると作物価格の高騰や飢餓の発生に直結し、社会不安や紛争の誘因ともなりかねません。
気候変動時代において、水資源の管理・配分や渇水への備え(ダムや地下水の持続的利用、早期警戒システムの整備など)はこれまで以上に重要な課題となっています。
海面上昇:沿岸部への脅威
海面上昇は異常気象とは少し性質が異なりますが、温暖化による「静かなる」脅威として見過ごせません。
気温上昇により海水が熱膨張すること、そして陸上の氷河や氷床が解けて海に流れ込むことで、海面は着実に上がり続けています。20世紀全体で見ると全球平均海面は約20cm上昇しました。その速度は近年加速しており、1901~1971年には年1.3mmだった上昇ペースが、2006~2018年には年3.7mmにまで早まっています。
現在も年4mm前後で上昇が進んでおり、この傾向は今後何世紀にもわたって続くと予想されています。
海面上昇の直接の影響としてまず懸念されるのが、沿岸域での高潮・浸水被害の増加です。わずかな海面上昇でも普段の満潮位が高くなり、台風や嵐の際にはこれまでより低い堤防でも越水・決壊しやすくなります。
実際、沿岸洪水(高潮など)の発生頻度は1960年代に比べ倍増しており、今後も沿岸部では洪水が「当たり前」のようになる恐れがあります。
例えば南太平洋のツバルやキリバス、インド洋のモルディブといった低平な島国では、高波や満潮時の浸水が常態化しつつあります。マーシャル諸島のように平均海抜がわずか数メートルの国では、このままでは本世紀中にも国土が水没しかねないとの研究報告もあります。
実際、マーシャル諸島では「2080年にも国が水の下に沈む可能性がある」と指摘され、現地の気候担当官は「私たちの国は非常に小さなカヌーで最前線にいる」と危機感を表明しています。
海面上昇はまた、塩水が地下水に浸入して農業用水が使えなくなる「塩害」や、海岸の侵食(ビーチの消失)など長期的な問題も引き起こします。
日本でも高潮による浸水想定域は拡大しており、東京湾岸や大阪湾岸をはじめとする都市圏の沿岸防災は待ったなしの課題です。防潮堤のかさ上げやポンプ設備の充実、土地利用の見直しなどハード・ソフト両面の対策が求められます。

将来予測:温暖化1.5℃、2℃、3℃、4℃のシナリオ
気候変動の影響は、将来の温暖化の程度によって大きく異なります。
国際的にはパリ協定で「今世紀末の気温上昇を2℃未満、できれば1.5℃に抑える」目標が掲げられていますが、現状の取り組みではこのままでは3~4℃の上昇に向かう恐れが指摘されています。
ここでは気温上昇幅ごとに想定される未来を概観し、異常気象リスクがどのように変わるかを見てみましょう。
1.5℃上昇の世界
産業革命前からの気温上昇を1.5℃以内に収められれば、気候変動の影響はある程度抑制されます。
しかしそれでも現在(+1.1℃程度)より若干進むため、今よりさらに極端な現象が増えることは避けられません。
例えば熱波の頻度は今より高くなり、平均的な暑い季節がより長引き、寒い季節は短縮します。大雨や干ばつも地域によってはさらに強まると予想されます。それでも1.5℃に抑えられれば、影響はまだ緩和的です。
たとえばサンゴ礁への打撃を見ると、1.5℃上昇では全体の70~90%が白化する(死滅またはダメージを受ける)と見込まれるのに対し、後述の2℃上昇ではほぼ99%以上のサンゴ礁が消滅すると予測されています。
このようにわずか0.5℃の違いでも影響は大きく異なるため、1.5℃目標を追求することには科学的にも大きな意義があるとされています。
2℃上昇の世界
2℃の温暖化まで進行すると、気候変動の影響は1.5℃に比べて著しく深刻化します。
極端な高温現象についてIPCCは「2℃の世界では、人体や農業にとって重大な閾値を超える猛暑がより頻繁に発生する」と警告しています。
具体的には、真夏の最高気温が現在よりさらに何度も上回り、世界の様々な地域で致命的な熱波が今以上の頻度で起こるでしょう。
水不足や食糧生産への悪影響も顕著になり、例えば中東や南アジアでは真夏日に屋外で活動すること自体が危険となる日数が増えると予想されます。また、1.5℃ではギリギリ持ちこたえた生態系や動植物種も、2℃では耐えきれずに大規模な絶滅や生息域縮小が起こるリスクが高まります。前述のサンゴ礁が顕著な例で、2℃上昇ではほぼ全滅的な被害が見込まれています。
さらに海面上昇については、2100年までに約50cm前後の上昇が見込まれ、100年に一度の高潮氾濫が毎年のように起こる沿岸も出てくると懸念されています。
3℃上昇の世界
3℃もの上昇となると、地球の気候は現在から一変してしまいます。
欧州や北米など多くの地域で今より酷暑がさらに数℃上乗せされ、平均的な夏でも猛暑日が続出するでしょう。
農業生産への影響が深刻化し、トウモロコシや小麦など主要作物の平均収量が低下するとの試算もあります。また海面上昇は2100年までに70cm前後に達すると見られ、低地の沿岸都市では毎年のように大規模な浸水被害に悩まされる可能性があります。
3℃を超えると、科学者が懸念する「ティッピングポイント(臨界点)」に達するリスクも無視できません。
ティッピングポイントとは、気候システムの一部が不可逆的に大きく変化してしまう転換点のことです。例えばグリーンランドや南極の氷床は一定以上温度が上がると大規模融解が止まらなくなり、数世紀かけて海面を数メートル上昇させてしまう可能性があります。またアマゾン熱帯雨林が乾燥化で砂漠に近い状態へ変貌したり、北極海の夏の海氷が完全になくなったりすることも考えられます。
IPCC第6次報告書でも「温暖化レベルが高くなるほど、起こり得る変化が急激かつ不可逆的になる可能性が高まる」とされています。
3℃上昇の世界では、そうした低い確率だが壊滅的影響をもたらす事態(いわゆるテールリスク)にも注意を払わねばならなくなります。
4℃上昇の世界
4℃を超えるレベルの温暖化は、現代文明にとって想像を絶する過酷な未来です。
高温・豪雨・干ばつ・海面上昇などあらゆる気候影響が重層的に襲い、人類社会の適応能力を超えてしまう地域も出てくるでしょう。
夏の平均気温が現在より5℃近く高くなる地域もあり、熱帯や亜熱帯の一部では従来の気候帯では類を見ない酷暑が常態化します。2100年までの海面上昇は1m近くに達するシナリオもありえます。
また、この水準まで気温が上がると大陸氷床の不安定化が現実味を帯び、2100年以降に海面がさらに数メートル単位で上昇することも十分考えられます。
過去に地球が現在より3~4℃暖かかった数百万年前の地質時代には、海面が現在より5~25m高かったという科学的知見もあります。
4℃上昇はそうした遠い過去の地球環境に匹敵し、人類のみならず地球上の生態系の大部分が現在の形を保てなくなるほどの激変です。
幸い、世界はこうした最悪シナリオを回避すべく動いています。
仮に各国が掲げる脱炭素目標を達成できれば、今世紀の温暖化を2~3℃程度に抑えられる可能性もあります。
しかしどのシナリオであっても、今後数十年は気候変動の進行に伴うリスクが確実に高まる点に留意が必要です。たとえ1.5℃に抑えたとしても、現在より影響が大きくなることは避けられません。重要なのは、温暖化の程度をできる限り低く抑えつつ、同時に不可避な影響に対して社会が備えることです。

増え続ける災害と支援のこれから
このように気候変動による異常気象のリスクは高まる一方であり、災害への備えや支援の重要性も飛躍的に増しています。
頻発する大規模災害に対応するため、各国の政府機関や国際機関、NPOなどが救援・支援活動に奔走しています。
先述のとおり、1970年以降で見ると気象災害の件数は5倍にも増えました。被災者を救う最後の砦である人道支援や災害救助のニーズも、それに応じて膨らみ続けています。例えば2022年のパキスタン洪水では国際的な支援要請が行われ、各国の援助物資や寄付が被災数千万の人々を支えました。
しかし同時期に他の国でも災害が起こればリソースは分散せざるを得ず、支援の手が追いつかない事態も現実に起きています。
幸い、防災インフラや早期警戒システムの整備によって、人命被害を減らすことには一定の成功を収めています。
WMOによれば、過去50年で災害による死者数は3分の1に減少しました。これは各国の防災体制強化や予報技術の進歩、地域コミュニティでの備えなどの成果と言えます。
一方で経済的被害は増大の一途であり、気候変動に伴う損失と損害(ロス&ダメージ)は深刻な問題として国際議題にもなっています。今後、温暖化が進むほど複数の災害が同時多発して複合災害となるリスクも高まり、災害対応の難易度は上がるでしょう。
こうした中、私たち一人ひとりにもできる備えがあります。
まずは気候変動による災害リスクの現実を正しく理解することが出発点です。本記事で述べたような科学的知見を踏まえ、自分の住む地域ではどのような危険が高まるのか、行政や専門家が発信する情報に目を向けてみましょう。
そして災害時に被害を減らす行動(ハザードマップの確認、避難経路の確保、非常用品の備蓄など)をとることも大切です。
また、信頼できる災害救援のNPOや募金先に継続的に寄付したり、ボランティアとして支援活動に参加したりすることも、異常気象時代にお互いを支え合う一つの形です。気候変動による災害はもはや他人事ではなく、「いつ・どこで誰が」被災してもおかしくありません。
社会全体で知恵とリソースを出し合い、備えることで被害を最小化し、適応していくことがこれからの課題です。
異常気象時代は決して容易な未来ではありません。
しかし、私たちにはまだ時間と手段があります。科学が示す現実を直視しつつ、一人ひとりが関心を持ち、行動することで被害の軽減や気候変動そのものの緩和につなげることも可能です。
未来世代により安全な地球を引き継ぐために、まずは現状を正しく理解し、できるところから備えていきましょう。本記事がその一助となれば幸いです。
【参考資料】気象庁・環境省・IPCC報告書・WMOレポート・World Weather Attribution分析結果・各種報道よりjma.go.jpwmo.intjamstec.go.jpwmo.intwmo.intworldweatherattribution.orgworldweatherattribution.orgfastcompany.comtohoku.env.go.jpgreenpeace.orgworldweatherattribution.orgworldweatherattribution.orgindependent.co.ukipcc.chall4inc.comipcc.ch