私たちの地球を覆う緑の森林は、今この瞬間も静かに、しかし確実に失われ続けています。
国連の最新報告によると、2015年以降、世界では毎年約10万平方キロメートルの天然林が消失しており、これは東京都と同じ面積の森が1週間ごとに地球上から姿を消していることを意味します。
この深刻な森林減少の背景には、気候変動や違法伐採といった直接的な要因だけでなく、森林を守るべき人材の深刻な不足という、あまり注目されていない根本的な問題が存在しています。
日本においても、国土の約67%を占める豊かな森林資源を抱えながら、その管理と保護を担う専門人材の不足が年々深刻化しています。
林業従事者数は1980年の約14万人から2020年には約4万5千人まで減少し、その平均年齢は52歳を超えています。この人材不足は単なる労働力の問題を超えて、森林の持続可能な管理、生物多様性の保全、そして私たちの生活を支える森林の多面的機能の維持に深刻な影響を与えています。
しかし、この危機的状況に対して、新たな希望の光が見えてきています。
それは、市民や企業からの寄付を通じた森林保護人材の育成と支援です。従来の政府予算や補助金制度だけでは限界のある森林保護事業に、民間からの資金が新たな可能性をもたらしています。
今回は、森林保護における人材不足の実態を詳しく分析し、寄付という手段がいかにしてこの社会課題の解決に貢献できるかを探ります。
目次
第1章:森林保護人材不足の深刻な実態
1.1 数字で見る人材不足の現状
森林保護に携わる人材の不足は、単なる統計上の問題ではありません。それは私たちの生活基盤を支える森林生態系の維持管理に直接的な影響を与える、緊急性の高い社会課題です。
日本の林業従事者数の推移を見ると、その減少傾向は驚くべき速度で進行しています。1960年には約44万人いた林業従事者は、2020年には約4万5千人まで減少し、60年間で約90%もの人材が失われました。
この減少率は他の産業と比較しても異常に高く、農業従事者の減少率(約75%)を大きく上回っています。
さらに深刻なのは、残された従事者の高齢化です。林業従事者の年齢構成を見ると、65歳以上が全体の約25%を占める一方、35歳未満の若年層は約20%にとどまっています。
この年齢構成は、今後10年から15年の間に大量退職が予想されることを意味しており、現在の人材不足がさらに加速する可能性が高いことを示しています。
地域別に見ると、人材不足の状況はより深刻です。特に中山間地域では、森林面積当たりの管理人員が都市近郊の森林と比較して著しく少なく、適切な管理が行き届かない森林が増加しています。
北海道、東北、中国・四国地方などの森林率の高い地域ほど、人材不足による管理の空白地帯が拡大している傾向が見られます。
1.2 専門技術者の不足とその影響
森林保護には、単純な労働力だけでなく、高度な専門知識と技術を持った人材が不可欠です。
森林計画の策定、生態系の調査、病害虫の防除、適切な間伐の実施など、これらの業務には長年の経験と専門的な教育を受けた技術者が必要です。
しかし、現在の日本では森林技術者の養成機関自体が縮小傾向にあります。林業系の大学学科や専門学校の定員は過去20年間で約30%減少し、卒業生の多くも林業以外の分野に就職するケースが増えています。
この結果、森林管理に必要な技術の継承が困難になり、現場での判断力や問題解決能力を持った人材の確保がますます困難になっています。
特に深刻なのは、森林病害虫の専門家や野生動物管理の専門家の不足です。近年、気候変動の影響で森林病害虫の発生パターンが変化し、従来とは異なる対策が必要になっていますが、これに対応できる専門家が圧倒的に不足しています。
また、シカやイノシシなどの野生動物による森林被害が拡大する中、適切な個体数管理や被害防止対策を実施できる専門家の不足も深刻な問題となっています。
1.3 財政制約が生む悪循環
森林保護人材の不足は、財政的な制約と密接に関連しています。多くの地方自治体では、厳しい財政状況の中で森林管理予算の削減を余儀なくされており、これが人材確保をさらに困難にする悪循環を生んでいます。
林野庁の調査によると、市町村の森林管理予算は過去10年間で平均約15%削減されており、特に人件費の削減が顕著です。
この結果、森林管理に従事する職員の待遇改善が進まず、若い人材の確保が困難になっています。林業従事者の平均年収は約350万円と、全産業平均の約430万円を大きく下回っており、この待遇格差が人材流出の大きな要因となっています。
また、森林組合などの現場組織でも、組合員の減少や木材価格の低迷により、十分な人件費を確保することが困難になっています。
多くの森林組合では、正規職員の採用を控え、臨時職員やパートタイム職員に依存する傾向が強まっており、これが技術の継承や組織の持続性に深刻な影響を与えています。
1.4 地域格差の拡大
森林保護人材の不足は、地域間の格差を拡大させる要因ともなっています。
都市部に近い森林では比較的人材確保が容易である一方、過疎化が進む中山間地域では深刻な人材不足に直面しています。
特に問題となっているのは、森林所有者の高齢化と不在村化です。
森林所有者の約40%が65歳以上となっており、その多くが都市部に居住しているため、森林の管理に直接関与することが困難になっています。この結果、地域の森林組合や林業事業体に管理を委託するケースが増えていますが、これらの組織自体も人材不足に悩んでおり、適切な管理が行き届かない森林が増加しています。
また、山間地域では若年人口の流出が続いており、森林管理の担い手となる地域住民自体が減少しています。これまで地域コミュニティが担ってきた森林の見回りや簡易な管理作業も、人手不足により継続が困難になっているケースが多く見られます。
このような地域格差の拡大は、森林の管理水準の地域間格差を生み、結果として森林の多面的機能の発揮にも地域差が生じる原因となっています。
水源涵養や土砂災害防止などの公益的機能は、特定の地域だけでなく下流域や広域にわたって影響を与えるため、この格差は社会全体の問題として捉える必要があります。

第2章:人材不足が森林に与える深刻な影響
2.1 森林管理の質的低下とその連鎖反応
森林保護人材の不足は、森林管理の質的低下を引き起こし、それが様々な環境問題や社会問題の連鎖反応を生んでいます。適切な管理が行われない森林では、まず間伐作業の遅れが顕著に現れます。
間伐は森林の健全な成長を促進し、林内環境を改善する重要な作業ですが、人材不足により計画的な実施が困難になっています。林野庁の調査によると、間伐が必要とされる人工林のうち、実際に間伐が実施されているのは年間約60%程度にとどまっており、残りの40%は管理が遅れている状況です。
間伐の遅れは、森林の過密化を招き、個々の樹木の成長を阻害します。過密な森林では日光が林床まで届かず、下層植生の発達が妨げられるため、生物多様性の低下や土壌の流出リスクの増大につながります。
また、樹木同士の競争が激化することで、病害虫に対する抵抗力が低下し、森林全体の健全性が損なわれる結果となります。
さらに深刻なのは、森林病害虫の早期発見と対策の遅れです。専門知識を持った技術者の不足により、病害虫の発生初期段階での発見が困難になり、被害が拡大してから対策を講じるケースが増えています。
近年問題となっているナラ枯れ被害やマツ材線虫病の拡大も、人材不足による監視体制の不備が一因となっています。
2.2 災害リスクの増大と社会への影響
適切な管理が行われない森林は、自然災害のリスクを大幅に増大させます。特に、土砂災害や洪水の発生確率の上昇は、森林周辺地域だけでなく、下流域の住民にとっても深刻な脅威となっています。
森林の土砂災害防止機能は、樹木の根系による土壌の緊縛効果と、適切な林床管理による表面流出の抑制によって発揮されます。
しかし、人材不足により間伐や下刈りなどの管理作業が適切に行われない森林では、この機能が著しく低下します。
実際に、近年発生した土砂災害の被災地を調査すると、管理不足の人工林が崩壊の起点となっているケースが多く確認されています。
2018年の西日本豪雨では、適切な管理が行われていない人工林での土砂災害発生率が、管理された森林と比較して約3倍高いという調査結果が報告されています。
また、森林の水源涵養機能の低下も深刻な問題です。適切に管理された森林は、降雨を一時的に蓄え、徐々に河川に放出することで洪水の緩和と渇水の防止に貢献します。しかし、管理不足により林床の保水力が低下した森林では、この機能が十分に発揮されず、下流域での洪水リスクの増大や水質の悪化を招いています。
2.3 生物多様性への深刻な影響
森林は地球上の陸域生物種の約80%が生息する重要な生態系ですが、人材不足による管理の質的低下は、この生物多様性に深刻な影響を与えています。
適切な森林管理は、様々な生物の生息環境を維持・創出する役割を果たします。
例えば、計画的な間伐により林内に適度な光環境を作り出すことで、多様な植物種の生育を促進し、それを基盤とした豊かな生態系を維持することができます。しかし、人材不足により管理が行き届かない森林では、単調な環境となり、生物多様性の低下が進行しています。
特に深刻なのは、希少種の生息地の管理不足です。多くの希少な動植物は、特定の森林環境に依存して生存しており、その環境の維持には専門的な知識と継続的な管理が必要です。
しかし、専門技術者の不足により、これらの希少種の生息地管理が適切に行われないケースが増加しており、絶滅リスクの増大が懸念されています。
また、外来種の侵入防止と駆除も、専門知識を持った人材が不足することで困難になっています。
外来植物の早期発見と適切な駆除には、在来種との識別能力と効果的な駆除技術が必要ですが、これらの技術を持った人材の不足により、外来種の拡大を防ぐことが困難になっているケースが各地で報告されています。
2.4 経済的損失の拡大
森林保護人材の不足は、直接的な経済損失も生み出しています。
適切な管理が行われない森林では、木材の品質低下や収量減少により、林業経営の収益性が大幅に悪化します。
間伐の遅れにより過密化した森林では、個々の樹木の成長が阻害され、最終的な木材収量が大幅に減少します。林業経済研究所の試算によると、適切な間伐が行われない人工林では、最終収量が適正管理された森林と比較して30~50%減少する可能性があるとされています。
また、病害虫被害の拡大による経済損失も深刻です。
早期発見と適切な対策が行われれば最小限に抑えられる被害も、専門技術者の不足により対応が遅れることで、被害が広域に拡大し、復旧に要する費用が大幅に増加します。ナラ枯れ被害による経済損失は、年間約100億円に達するとの試算もあり、これらの多くは適切な人材配置により予防可能な損失と考えられています。
さらに、森林の公益的機能の低下による間接的な経済損失も無視できません。
水源涵養機能の低下による水道事業への影響、土砂災害防止機能の低下による防災事業費の増大、観光資源としての森林の価値低下など、その影響は多岐にわたります。
これらの経済損失を総合すると、森林保護人材の不足による年間の経済損失は数千億円規模に達する可能性があると推計されています。
2.5 気候変動対策への影響
森林は重要な炭素吸収源として、気候変動対策において中核的な役割を果たしています。
しかし、人材不足による管理の質的低下は、森林の炭素吸収能力にも深刻な影響を与えています。
適切に管理された森林は、樹木の健全な成長により大量の二酸化炭素を吸収・固定します。
しかし、間伐などの管理作業が適切に行われない森林では、樹木の成長が阻害され、炭素吸収能力が大幅に低下します。
環境省の調査によると、管理不足の人工林では、適正管理された森林と比較して炭素吸収量が約40%減少するという結果が報告されています。
また、病害虫被害や風倒被害により枯死した樹木は、蓄積していた炭素を大気中に放出するため、森林が炭素の吸収源から排出源に転じる可能性もあります。
人材不足により予防的な管理が困難になることで、このようなリスクが増大しており、日本の温室効果ガス削減目標の達成にも影響を与える可能性があります。
国際的にも、森林による炭素吸収は重要な気候変動対策として位置づけられており、適切な森林管理の実施は国際的な責務でもあります。人材不足による管理の質的低下は、この国際的な責務の履行にも支障をきたす可能性があり、長期的な視点からの対策が急務となっています。

第3章:寄付による森林保護人材支援の可能性
3.1 従来の支援制度の限界と新たなアプローチの必要性
これまで森林保護人材の育成と確保は、主に政府の補助金制度や公的な研修制度に依存してきました。しかし、厳しい財政状況の中で、これらの制度だけでは急速に進行する人材不足に対応することが困難になっています。
現在の主要な支援制度として、林野庁の「緑の雇用」事業があります。
この事業は新規就業者の研修費用を支援するもので、年間約1,500人の新規就業者を支援していますが、一方で年間約2,000人が離職しているため、全体としては人材の減少が続いています。
また、研修期間中の生活支援や、研修修了後の継続的なキャリア支援については十分とは言えない状況です。
地方自治体レベルでも、森林環境譲与税を活用した人材育成事業が実施されていますが、多くの自治体では予算規模が限定的で、抜本的な人材不足の解決には至っていません。特に、専門技術者の養成や、若手人材の定着支援については、公的制度だけでは限界があることが明らかになっています。
このような状況の中で、民間からの寄付による支援が新たな可能性を提供しています。
寄付による支援は、公的制度の制約を受けずに、より柔軟で効果的な人材育成プログラムを実現できる可能性があります。また、寄付者の意向を反映した特色ある支援プログラムの実施により、多様な人材の確保と育成が期待できます。
3.2 人材育成プログラムへの寄付支援
寄付による森林保護人材の育成支援は、既に各地で実践的な取り組みが始まっています。
これらの取り組みは、従来の公的制度では対応が困難だった分野での人材育成を可能にしており、その効果が注目されています。
専門技術者養成プログラムの支援
森林病害虫の専門家や野生動物管理の専門家など、高度な専門知識を必要とする分野での人材育成には、長期間の研修と実践的な経験が必要です。
公益財団法人森林文化協会では、企業や個人からの寄付を活用して、これらの専門分野での人材育成プログラムを実施しています。
このプログラムでは、大学や研究機関と連携して、最新の科学的知見に基づいた研修カリキュラムを提供しています。
参加者は2年間の研修期間中、生活費の支援を受けながら、理論学習と実地研修を組み合わせた包括的な教育を受けることができます。これまでに約200名の専門技術者を養成し、その多くが各地の森林管理の現場で活躍しています。
若手人材の定着支援
森林保護分野への若手人材の参入と定着を促進するため、寄付を活用した包括的な支援プログラムも実施されています。
NPO法人森づくりフォーラムでは、新規就業者に対する住居支援、研修費用の補助、メンター制度の提供などを組み合わせた支援を行っています。
このプログラムの特徴は、単なる技術研修にとどまらず、森林保護の意義や社会的価値についての教育も重視している点です。
参加者は森林の多面的機能や生物多様性保全の重要性について深く学ぶことで、単なる職業としてではなく、社会的使命感を持って森林保護に取り組む人材として成長しています。
女性人材の活用促進
従来男性中心だった森林保護分野において、女性人材の活用を促進する取り組みも寄付により支援されています。
一般社団法人日本森林技術協会では、女性向けの森林管理技術研修プログラムを実施し、子育て中の女性でも参加しやすい環境を整備しています。
このプログラムでは、託児サービスの提供や、パートタイム勤務に対応した研修スケジュールの設定など、女性のライフスタイルに配慮した支援を行っています。
また、女性ならではの視点を活かした森林環境教育や、きめ細かな生態系調査などの分野で、新たな専門性を発揮する人材の育成にも取り組んでいます。
3.3 技術革新への投資支援
森林保護の効率化と人材不足の解決には、最新技術の導入が不可欠です。
寄付による支援は、公的予算では導入が困難な先進技術の実用化を促進する重要な役割を果たしています。
ドローンを活用した森林監視システム
ドローンを活用した森林監視システムは、少ない人員で広大な森林を効率的に管理することを可能にします。
公益財団法人日本自然保護協会では、企業からの寄付を活用して、AI画像解析機能を搭載したドローンによる森林監視システムの開発と実用化を進めています。
このシステムでは、定期的なドローン飛行により森林の状況を撮影し、AI技術により病害虫の発生や違法伐採の兆候を自動的に検出します。
従来は専門技術者が徒歩で行っていた森林巡視を、大幅に効率化することができ、限られた人材でもより広範囲の森林管理が可能になっています。
IoTセンサーによる森林環境モニタリング
森林内に設置したIoTセンサーにより、温度、湿度、土壌水分などの環境データをリアルタイムで収集し、森林の健康状態を継続的に監視するシステムも、寄付により開発が進められています。
このシステムにより、病害虫の発生リスクの早期予測や、適切な管理作業のタイミングの判断が可能になります。また、収集されたデータは機械学習により分析され、より精度の高い森林管理計画の策定に活用されています。
VR技術を活用した研修システム
森林管理技術の習得には、実際の森林での経験が重要ですが、安全性や効率性の観点から、VR(仮想現実)技術を活用した研修システムの開発も進められています。
このシステムでは、様々な森林環境や作業状況を仮想空間で再現し、研修生が安全な環境で実践的な技術を学ぶことができます。また、熟練技術者の作業手順や判断プロセスをVRで記録・再現することで、技術の継承も効率的に行うことができます。
3.4 地域コミュニティの活性化支援
森林保護には、専門技術者だけでなく、地域住民の参加と協力が不可欠です。
寄付による支援は、地域コミュニティの森林保護活動を活性化し、持続可能な森林管理体制の構築に貢献しています。
市民参加型森林管理プログラム
都市住民と山間地域住民が協力して森林管理に取り組む市民参加型プログラムが、各地で寄付により支援されています。
認定NPO法人JUON NETWORKでは、企業や個人からの寄付を活用して、都市住民が週末に森林管理作業に参加するプログラムを実施しています。
このプログラムでは、専門技術者の指導の下で、都市住民が間伐や下刈りなどの作業に参加し、森林管理の実践的な技術を学びます。参加者は森林の重要性を体験的に理解するとともに、地域住民との交流を通じて森林保護への関心を深めています。
森林環境教育の推進
次世代の森林保護人材を育成するため、子どもたちを対象とした森林環境教育プログラムも寄付により支援されています。
公益社団法人国土緑化推進機構では、学校教育と連携した森林環境教育プログラムを全国で展開しています。
このプログラムでは、子どもたちが実際に森林を訪れ、樹木の成長過程や生態系の仕組みを学ぶとともに、森林管理作業を体験します。これらの体験を通じて、森林の重要性を理解し、将来的に森林保護分野への進路を選択する動機を提供しています。
ボランティア制度の充実
森林保護活動に参加するボランティアの育成と活動支援も、寄付により充実が図られています。
各地の森林組合や環境団体では、寄付を活用してボランティア向けの研修プログラムや活動支援制度を整備しています。
これらの制度により、退職後の高齢者や学生など、様々な立場の人々が森林保護活動に参加できる環境が整備されています。ボランティアの活動は、専門技術者の業務を補完し、限られた人材でもより効果的な森林管理を実現することに貢献しています。

第4章:具体的な寄付先と成功事例
4.1 信頼できる森林保護団体の選び方
森林保護への寄付を検討する際、最も重要なのは信頼できる団体を選択することです。適切な団体選択により、寄付金が効果的に森林保護人材の育成と支援に活用され、持続可能な成果を生み出すことができます。
透明性の高い財務管理
信頼できる森林保護団体の第一の条件は、財務管理の透明性です。
優良な団体では、寄付金の使途を詳細に公開し、定期的な活動報告書や財務報告書を発行しています。公益財団法人や認定NPO法人などの法的認定を受けている団体は、第三者による監査を受けており、財務管理の透明性が担保されています。
寄付を検討する際は、団体のウェブサイトで財務報告書を確認し、事業費と管理費の比率、具体的な事業内容と成果を詳細に検討することが重要です。
一般的に、事業費比率が80%以上の団体は、寄付金を効果的に活用していると評価できます。
実績と継続性
森林保護人材の育成には長期間を要するため、団体の実績と継続性も重要な選択基準です。
設立から一定期間が経過し、継続的な活動実績を持つ団体は、安定した運営基盤と豊富な経験を有しており、効果的な人材育成プログラムを実施できる可能性が高いと考えられます。
また、大学や研究機関、行政機関との連携実績も重要な指標です。これらの機関との協力関係は、科学的根拠に基づいた活動の実施と、社会的信頼性の確保につながります。
4.2 主要な森林保護団体と支援プログラム
公益財団法人森林文化協会

森林文化協会は、1974年に設立された歴史ある森林保護団体で、森林保護人材の育成において豊富な実績を有しています。
同協会では、企業や個人からの寄付を活用して、以下のような人材育成プログラムを実施しています。
「森林技術者養成プログラム」では、年間約50名の新規技術者を育成しており、2年間の研修期間中に月額15万円の生活支援金を支給しています。
研修内容は、森林生態学、森林計画学、森林病理学などの理論学習と、全国各地の森林での実地研修を組み合わせた包括的なカリキュラムとなっています。
また、「森林環境教育指導者養成プログラム」では、学校教育や社会教育の現場で森林環境教育を推進する指導者を育成しています。
このプログラムの修了生は、全国の小中学校や環境教育施設で活躍しており、次世代の森林保護意識の向上に貢献しています。
認定NPO法人森づくりフォーラム
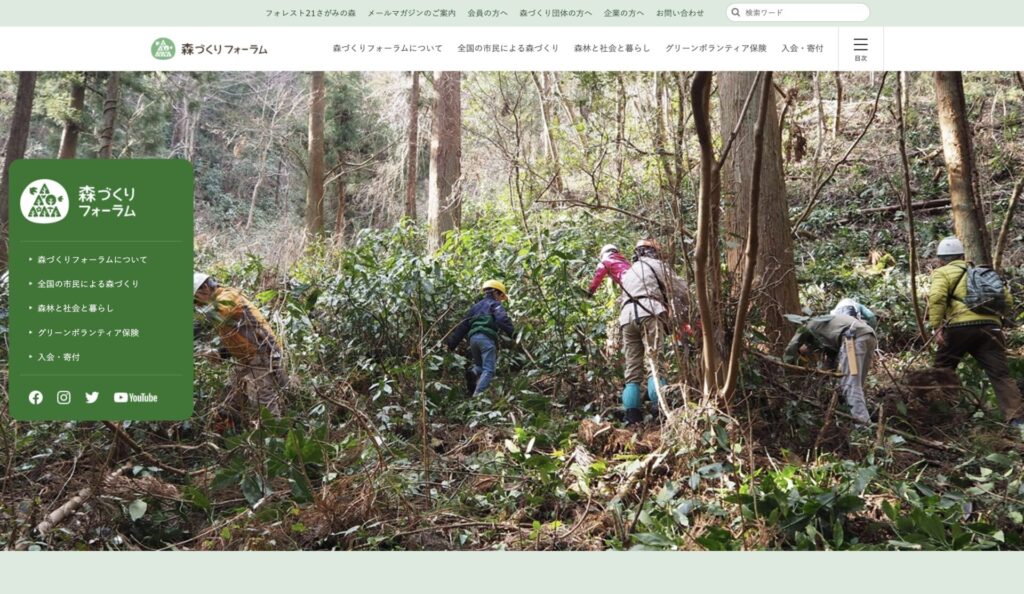
森づくりフォーラムは、市民参加による森林保護活動を推進する団体として、1999年に設立されました。
同団体では、寄付を活用して以下のような革新的な取り組みを実施しています。
「若手林業者定着支援プログラム」では、新規就業者に対する包括的な支援を行っています。
住居確保支援として月額3万円の家賃補助を2年間提供し、技術研修費用として年間50万円を支援しています。また、経験豊富な林業者をメンターとして配置し、技術指導だけでなく、キャリア相談や生活相談にも対応しています。
「女性林業者支援プログラム」では、女性の森林保護分野への参入を促進するため、託児サービス付きの研修プログラムや、パートタイム勤務に対応した柔軟な働き方の提案を行っています。
これまでに約100名の女性が同プログラムを修了し、その多くが森林組合や林業事業体で活躍しています。
一般社団法人日本森林技術協会

日本森林技術協会は、森林技術の向上と普及を目的として1962年に設立された専門技術団体です。同協会では、最新技術を活用した効率的な森林管理手法の開発と普及に取り組んでいます。
「ICT森林管理技術者養成プログラム」では、ドローンやGIS(地理情報システム)、リモートセンシング技術を活用した森林管理技術を習得できる研修を実施しています。
このプログラムの修了生は、従来の手法と比較して約3倍の効率で森林調査を実施できるようになり、人材不足の解決に大きく貢献しています。
また、「森林病害虫診断技術者養成プログラム」では、最新の分子生物学的手法を用いた病害虫の早期診断技術を教育しています。このプログラムにより養成された技術者は、従来よりも迅速かつ正確な診断を行うことができ、被害の拡大防止に効果を上げています。
4.3 企業による森林保護基金の成功事例
トヨタ自動車「トヨタ環境チャレンジ2050」
トヨタ自動車は、2015年に発表した「トヨタ環境チャレンジ2050」の一環として、森林保護人材の育成に大規模な投資を行っています。
同社は2020年から2030年までの10年間で、総額100億円の森林保護基金を設立し、人材育成を中心とした支援を実施しています。
この基金では、全国の林業系大学と連携して奨学金制度を設立し、年間200名の学生に対して年額100万円の奨学金を支給しています。また、卒業後に森林保護分野に就職した学生に対しては、奨学金の返済を免除する制度も設けており、優秀な人材の確保に大きな効果を上げています。
さらに、同社の技術力を活かして、森林管理用の電動作業機械の開発と無償提供も行っています。これらの機械により作業効率が向上し、少ない人員でもより効果的な森林管理が可能になっています。
住友林業「スミリンの森」プロジェクト
住友林業は、創業以来の森林事業の経験を活かして、「スミリンの森」プロジェクトを展開しています。このプロジェクトでは、年間約20億円の予算を投じて、森林保護人材の育成と技術開発を支援しています。
同プロジェクトの特徴は、国内外の森林保護活動を統合的に支援している点です。国内では、森林組合との連携により若手技術者の育成プログラムを実施し、海外では熱帯林の保護と現地人材の育成を支援しています。
また、同社独自の森林管理技術を活用した研修プログラムも提供しており、参加者は最新の森林管理手法を実践的に学ぶことができます。
これまでに約500名の技術者がこのプログラムを修了し、全国各地の森林管理の現場で活躍しています。
ソフトバンク「森林×ICT」イニシアティブ
ソフトバンクは、ICT技術を活用した森林保護の革新を目指して、「森林×ICT」イニシアティブを立ち上げています。
このプロジェクトでは、年間約10億円の予算を投じて、ICT技術を活用した森林管理システムの開発と、それを操作できる人材の育成を支援しています。
同プロジェクトでは、5G通信技術を活用したリアルタイム森林監視システムの開発を進めており、ドローンやIoTセンサーから収集されるデータを瞬時に解析し、異常を検知するシステムを構築しています。
このシステムの操作技術者を育成するため、全国の林業系教育機関と連携した研修プログラムも実施しています。
まとめ:持続可能な森林保護に向けて
森林保護人材の不足は、単なる労働力の問題を超えて、私たちの生活基盤を支える森林生態系の持続可能性に関わる重要な社会課題です。
気候変動の進行、生物多様性の減少、自然災害の頻発化など、現代社会が直面する多くの環境問題の解決には、健全な森林の維持管理が不可欠であり、そのためには十分な数の専門技術者と、彼らを支える社会的基盤が必要です。
従来の政府主導の支援制度だけでは、急速に進行する人材不足に対応することは困難です。
しかし、市民や企業からの寄付による支援が加わることで、より柔軟で効果的な人材育成プログラムの実施が可能になり、森林保護の未来に新たな希望をもたらしています。
寄付による森林保護人材支援は、単なる慈善活動ではありません。
それは、私たち自身の生活環境を守り、次世代により良い地球環境を残すための投資です。森林が提供する清浄な空気、豊かな水資源、災害からの保護、そして多様な生物との共存の場は、すべて適切な森林管理によって維持されています。
一人ひとりの行動は小さくても、それが集まることで大きな変化を生み出すことができます。
月額1,000円の継続寄付、週末のボランティア参加、森林認証商品の選択など、私たちにできることは数多くあります。重要なのは、まず行動を始めることです。
森林保護人材の育成と支援は、長期的な取り組みが必要な分野です。しかし、今日始めた支援が、10年後、20年後の森林の姿を決定づけることになります。私たちの子どもたちや孫たちが、豊かな森林に囲まれた持続可能な社会で生活できるよう、今こそ行動を起こす時です。

