「ファンドレイジング」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
近年、NPOや社会課題解決に取り組む団体の間で注目を集めているこの概念は、単なる資金調達を超えて、社会を変える力を持つ重要な活動として認識されています。
日本ファンドレイジング協会によると、ファンドレイジングとは民間非営利団体が「活動のための資金を個人や法人、政府などから集める行為」と定義されています。
しかし、その本質は資金を集めることだけではありません。社会課題への理解と共感を広げ、多くの人々を社会変革の担い手として巻き込む、コミュニケーション活動でもあるのです。
今回は、ファンドレイジングの基本概念から具体的な手法、日本での成功事例まで、包括的に解説します。
社会課題解決に関心のある方、NPOでの活動を考えている方、そして寄付を通じて社会貢献したい方にとって、ファンドレイジングの理解は必要不可欠な知識となるでしょう。
目次
第1章:ファンドレイジングの基本概念
1.1 ファンドレイジングとは何か
ファンドレイジング(Fundraising)は、直訳すると「資金調達」を意味する英語です。しかし、営利企業が行う一般的な資金調達とは根本的に異なる特徴を持っています。
営利企業の資金調達では、投資家は将来的な経済的リターンを期待して資金を提供します。一方、ファンドレイジングにおける支援者は、経済的利益ではなく社会的価値の創造に共感し、資金を提供するのです。
日本ファンドレイジング協会は、ファンドレイジングを狭義と広義に分けて定義しています。狭義には寄付金のみを対象とした資金集めを指しますが、広義には寄付に加え、会費、助成金、補助金などの「支援的資金」集めも含むとされています。
1.2 対象となる組織
ファンドレイジングの主な対象となるのは、以下のような民間非営利団体です:
NPO法人(特定非営利活動法人) 市民が自発的に設立し、社会課題解決に取り組む法人格を持つ団体です。現在、日本には約5万のNPO法人が存在し、福祉、教育、環境、国際協力など多様な分野で活動しています。
公益法人 公益社団法人や公益財団法人として認定された団体で、より厳格な公益性の要件を満たしています。税制上の優遇措置も充実しており、寄付者にとってもメリットがあります。
社会福祉法人 社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で、高齢者介護、障害者支援、児童福祉などの分野で重要な役割を果たしています。
大学・研究機関 教育や研究活動の充実を目的とした資金調達も、ファンドレイジングの重要な領域です。特に私立大学では、施設整備や奨学金制度の充実のために積極的にファンドレイジングを行っています。
1.3 ファンドレイジングの社会的意義
ファンドレイジングは単なる資金調達手段を超えて、重要な社会的意義を持っています。
市民社会の参加促進
ファンドレイジングを通じて、多くの市民が社会課題解決に参加する機会が生まれます。寄付という行為は、金銭的支援だけでなく、社会課題への関心と理解を深める契機となります。
公的資金の補完
政府や自治体の予算だけでは対応困難な社会課題に対して、民間資金による柔軟で迅速な対応が可能になります。特に新しい社会課題や、制度の隙間に落ちる問題に対して、ファンドレイジングは重要な役割を果たします。
イノベーションの促進
民間資金による支援は、既存の制度にとらわれない革新的な取り組みを可能にします。リスクを取った挑戦的な活動も、ファンドレイジングによって実現できるのです。
1.4 資金の種類と特徴
ファンドレイジングで調達される資金には、以下のような種類があります:
寄付金
個人や法人からの無償提供による資金で、ファンドレイジングの中核を成します。一回限りの寄付から継続的な寄付まで、様々な形態があります。
会費
団体の会員から定期的に徴収する資金で、安定的な収入源として重要です。会員は資金提供だけでなく、団体の活動に参加する権利も得られます。
助成金
財団や企業が設立した基金からの支援で、特定の目的や条件を満たすプロジェクトに対して提供されます。競争的な選考プロセスを経ることが一般的です。
補助金
政府や自治体からの公的支援で、政策目標に合致する活動に対して提供されます。申請手続きが複雑な場合が多いですが、大きな金額の支援を受けられる可能性があります。
事業収入
サービスの提供や商品の販売による収入で、持続可能な運営のために重要な要素です。社会的企業やソーシャルビジネスでは、この比重が高くなります。

第2章:ファンドレイジングの手法と戦略
2.1 ファンドレイジングの3つの類型
効果的なファンドレイジングを実施するためには、適切な手法の選択が重要です。
ファンドレイジングの手法は、大きく3つの類型に分類できます。
営業型ファンドレイジング
直接的な営業活動による資金調達手法です。個別の面談や電話による寄付依頼、企業への提案営業などが含まれます。人的リソースを集中的に投入する必要がありますが、大口寄付の獲得には最も効果的な手法です。
金融型ファンドレイジング
金融商品や仕組みを活用した資金調達手法です。遺贈寄付、信託を活用した寄付、株式寄付などが含まれます。専門的な知識が必要ですが、大きな金額の寄付を受けられる可能性があります。
広報型ファンドレイジング
広報手法を用いた資金調達で、多くの人に向けて寄付を呼びかける手法です。ダイレクトメール、SNS、イベント、クラウドファンディングなどが含まれます。一度に多くの人にアプローチできる利点があります。
2.2 クラウドファンディング型の寄付
クラウドファンディングは、インターネットを通じて不特定多数の人から資金を調達する手法で、近年急速に普及しています。
購入型クラウドファンディング
支援者がプロジェクトに資金を提供し、その見返りとして商品やサービスを受け取る形式です。Readyfor、CAMPFIRE、Makuakeなどのプラットフォームが代表的です。
寄付型クラウドファンディング 純粋な寄付として資金を提供する形式で、税制上の優遇措置を受けられる場合があります。ふるさと納税も広義の寄付型クラウドファンディングと言えます。
2.3 会員制度の構築
継続的で安定した収入源として、会員制度の構築は重要な戦略です。
会員は定期的な会費を支払うだけでなく、団体の活動に参加し、ミッションの実現に貢献します。
会員制度の種類
•個人会員: 一般市民を対象とした会員制度
•法人会員: 企業や団体を対象とした会員制度
•学生会員: 学生向けの割引料金での会員制度
•賛助会員: より高額な会費で特別な特典を提供する制度
会員制度成功の要因
•明確な価値提供: 会員になることのメリットの明確化
•適切な会費設定: 提供価値に見合った料金設定
•継続的なコミュニケーション: 定期的な活動報告と交流機会の提供
•会員特典の充実: 限定イベントや情報提供などの特典
第3章:日本のファンドレイジング成功事例
3.1 日本ファンドレイジング大賞受賞事例
日本ファンドレイジング協会は毎年、優れたファンドレイジング活動を行った団体を顕彰する「日本ファンドレイジング大賞」を実施しています。
これらの受賞事例から、成功するファンドレイジングの要素を学ぶことができます。
第15回(2025年)大賞:ほくりくみらい基金「能登とともに基金」
2024年1月1日に発生した能登半島地震を受けて設立された「能登とともに基金」が、第15回日本ファンドレイジング大賞を受賞しました。この基金は、災害復興支援における迅速で効果的なファンドレイジングの模範例として高く評価されています。
成功要因の分析:
•迅速な対応: 災害発生直後の迅速な基金設立
•明確な使途: 復興支援の具体的な用途の明示
•地域との連携: 地元のニーズに基づいた支援活動
•透明性の確保: 寄付金の使途に関する詳細な報告
NPOによる1億円調達事例
日本のNPOがクラウドファンディングで1億円を調達した事例は、日本のファンドレイジング史上画期的な出来事でした。この成功は、以下の要因によるものと分析されています:
•社会的インパクトの大きさ: 多くの人が共感する社会課題への取り組み
•ストーリーテリングの巧みさ: 感情に訴える効果的な情報発信
•メディア戦略: マスメディアやSNSを活用した広範囲な宣伝
•支援者との関係構築: 既存の支援者ネットワークの活用
3.2 大学のファンドレイジング事例
日本の大学におけるファンドレイジングも近年活発化しており、国立大学の7割で学生支援主体の募金活動が実施されています。
海外大学の成功事例:UC Berkeley
カリフォルニア大学バークレー校では、コロンビア大学でのファンドレイジング経験がある学長をヘッドハントし、2012年には50名しかいなかったファンドレイザーを200名以上に増員しました。この大胆な人材投資により、同大学のファンドレイジング収入は大幅に増加しました。
日本の大学の取り組み
日本の大学でも、以下のような取り組みが進んでいます:
•専門人材の育成: ファンドレイザー資格取得の推進
•卒業生ネットワークの活用: 同窓会組織との連携強化
•企業との連携: 産学連携を通じた資金調達
•国際化への対応: グローバルな寄付者開拓
3.3 地域密着型NPOの事例
地域の課題解決に取り組む小規模なNPOでも、工夫次第で効果的なファンドレイジングをしています。
地域コミュニティとの連携
地域の商店街、自治会、学校などとの連携により、地域全体を巻き込んだファンドレイジング活動を展開しました。地域のお祭りやイベントと連携することで、多くの住民に活動を知ってもらう機会を創出しました。
小口寄付の積み重ね
大口寄付に頼らず、多くの地域住民からの小口寄付を積み重ねることで、安定した資金調達を実現しました。月額500円からの継続寄付制度を導入し、「地域の皆で支える」という意識を醸成しました。
ボランティアとの協働
資金だけでなく、時間や技能の提供も含めた包括的な支援体制を構築しました。ボランティアが友人や家族に活動を紹介することで、新たな支援者の獲得につながりました。
3.4 企業との連携事例
CSR活動との連携
企業の社会的責任(CSR)活動と連携したファンドレイジングも効果的な手法です。企業にとっては社会貢献活動の実績となり、NPOにとっては安定した資金源となる、Win-Winの関係を構築できます。
従業員参加型プログラム
企業の従業員が寄付を行い、企業が同額を上乗せする「マッチングギフト」制度を導入した事例があります。従業員が月額2,000円を寄付した場合、企業が同額を上乗せし、合計4,000円の寄付効果を生み出すことができます。
技能提供との組み合わせ
資金提供だけでなく、企業の専門技能やリソースの提供も含めた包括的な支援関係を構築した事例もあります。IT企業がシステム開発を支援し、広告代理店がマーケティング支援を行うなど、企業の本業を活かした支援が効果的です。
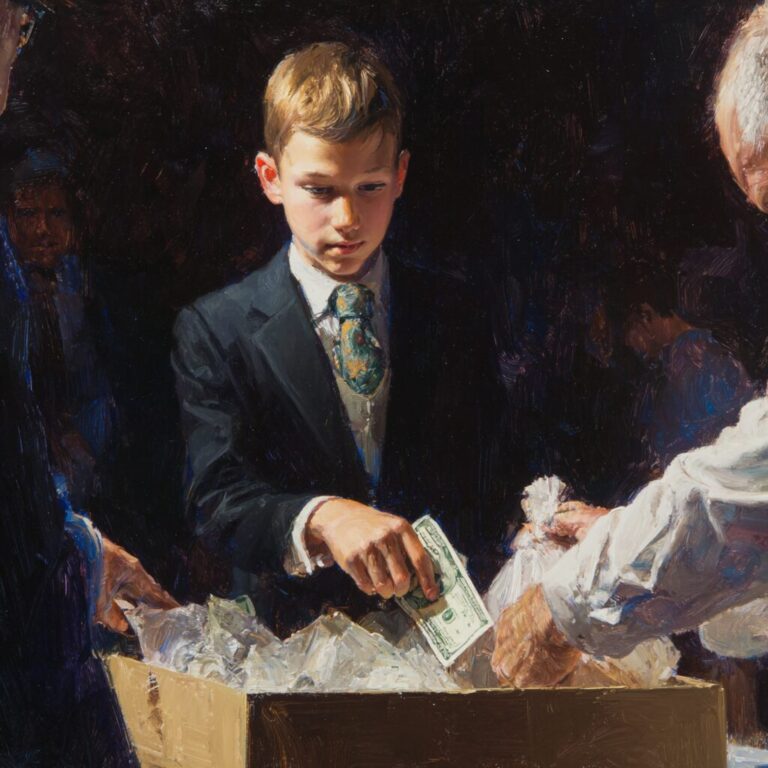
第4章:ファンドレイジングの課題と今後の展望
4.1 日本のファンドレイジング環境の現状
日本のファンドレイジング環境は、欧米諸国と比較して発展途上の段階にあります。この背景には、文化的、制度的な要因が複合的に影響しています。
寄付文化の成熟度
日本の個人寄付総額は約8,000億円程度とされており、GDP比では0.2%程度に留まっています。
これは、アメリカの2.1%、イギリスの0.5%と比較して大幅に低い水準です。
この背景には、以下のような文化的要因があります:
•公的サービスへの依存: 社会課題解決は政府の役割という意識の強さ
•寄付に対する認知不足: 寄付の社会的意義や効果に対する理解不足
•税制優遇の認知不足: 寄付金控除制度の存在や手続きに関する知識不足
制度的環境の改善 一方で、制度的環境は着実に改善されています:
•認定NPO法人制度: 寄付者への税制優遇措置の拡充
•ふるさと納税制度: 寄付文化の普及に貢献
•公益法人制度改革: より柔軟で透明性の高い制度への移行
4.2 デジタル技術の活用
デジタル技術の進歩により、ファンドレイジングの手法も大きく変化しています。
オンラインプラットフォームの活用
クラウドファンディングプラットフォームの普及により、小規模な団体でも効果的な資金調達が可能になりました。Readyfor、CAMPFIRE、ふるさとチョイスなど、多様なプラットフォームが利用できます。
SNSマーケティング
Facebook、Twitter、InstagramなどのSNSを活用したファンドレイジングが一般化しています。特に若年層へのアプローチには不可欠な手法となっています。
データ分析の活用
寄付者データの分析により、より効果的なアプローチが可能になっています。寄付履歴、属性情報、行動パターンなどを分析し、個別化されたコミュニケーションを実現できます。
ブロックチェーン技術
寄付金の透明性確保や国際送金の効率化において、ブロックチェーン技術の活用も検討されています。寄付金の使途を追跡可能にすることで、支援者の信頼を高める効果が期待されます。
4.3 国際的な動向と日本への示唆
アメリカの動向
アメリカでは、個人寄付総額が年間約40兆円に達し、GDP比で2%を超えています。この背景には、以下のような要因があります:
•税制優遇の充実: 寄付金控除の上限が高く設定されている
•寄付文化の定着: 宗教的背景や社会的責任意識の高さ
•プロフェッショナルの存在: 高度な専門性を持つファンドレイザーの活躍
ヨーロッパの動向 ヨーロッパでは、政府との協働による社会課題解決が進んでいます:
•社会的投資: 社会的リターンを重視した投資の拡大
•ソーシャルボンド: 成果連動型の資金調達手法の普及
•EU レベルでの制度整備: 国境を越えた寄付の促進
アジアの動向 アジア諸国でも、経済発展に伴いファンドレイジングが活発化しています:
•中国: デジタル技術を活用した革新的な手法の開発
•韓国: 企業の社会貢献活動との連携強化
•シンガポール: 政府主導による寄付文化の促進
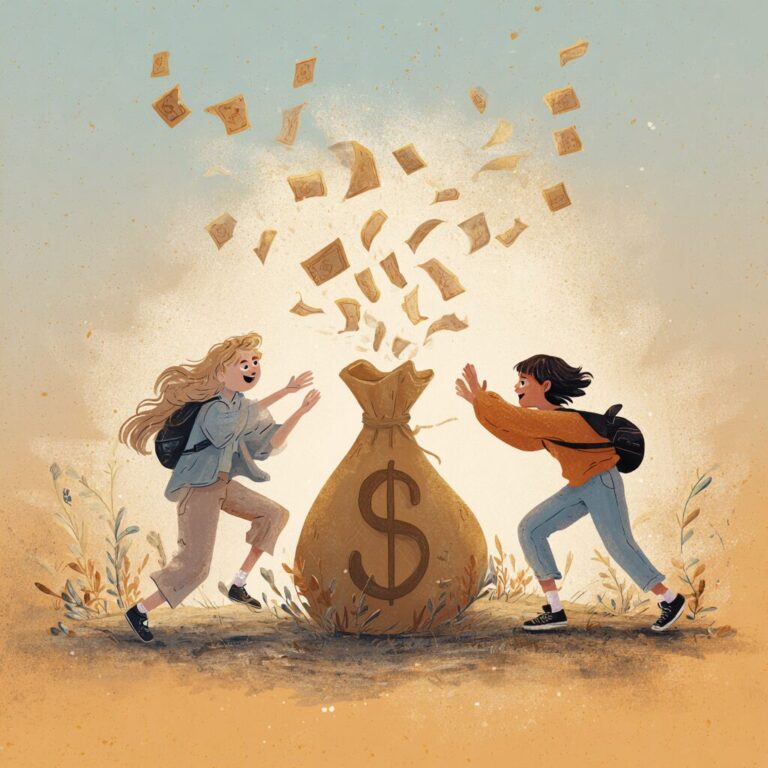
まとめ:ファンドレイジングが創る未来
ファンドレイジングの本質的価値
ファンドレイジングは単なる資金調達手段ではありません。
それは、社会課題に対する関心と理解を広げ、多くの人々を社会変革の担い手として巻き込む、重要なコミュニケーション活動なのです。
寄付という行為を通じて、支援者は社会課題の当事者となり、解決に向けた責任を共有します。この過程で、社会全体の課題解決能力が向上し、より良い社会の実現に向けた基盤が構築されます。
多様な参加の機会
ファンドレイジングは、経済的な支援だけでなく、時間、技能、ネットワークなど、様々な形での社会参加を可能にします。月額1,000円の小額寄付から、専門技能を活かしたプロボノ活動まで、一人ひとりの状況に応じた参加方法があります。
この多様性こそが、ファンドレイジングの大きな強みです。誰もが自分なりの方法で社会貢献に参加でき、その積み重ねが大きな社会変革を生み出すのです。
持続可能な社会の構築
ファンドレイジングによって調達された資金は、持続可能な社会の構築に向けた重要な投資となります。環境問題、貧困、教育格差、高齢化など、現代社会が直面する複雑な課題の解決には、政府だけでなく、市民社会の積極的な参加が不可欠です。
ファンドレイジングは、この市民参加を促進し、社会課題解決のためのリソースを効率的に配分する仕組みとして機能します。
今、始められること
ファンドレイジングに関わる方法は多様です:
支援者として
•関心のある社会課題に取り組む団体への寄付
•クラウドファンディングプロジェクトへの参加
•ボランティア活動への参加
実践者として
•所属する団体でのファンドレイジング活動の企画・実施
•認定ファンドレイザー資格の取得
•ファンドレイジングに関する学習と実践
推進者として
•ファンドレイジングの社会的意義の普及
•寄付文化の醸成に向けた活動
•制度改善に向けた提言活動
最後に
ファンドレイジングは、より良い社会を創るための重要なツールです。しかし、それは単なる手段に過ぎません。重要なのは、その背後にある「社会を良くしたい」という想いと、「みんなで力を合わせれば変えられる」という信念です。
一人ひとりの小さな行動が、やがて大きな社会変革につながります。ファンドレイジングを通じて、私たち一人ひとりが社会変革の主体となり、持続可能で公正な社会の実現に向けて歩んでいきましょう。

