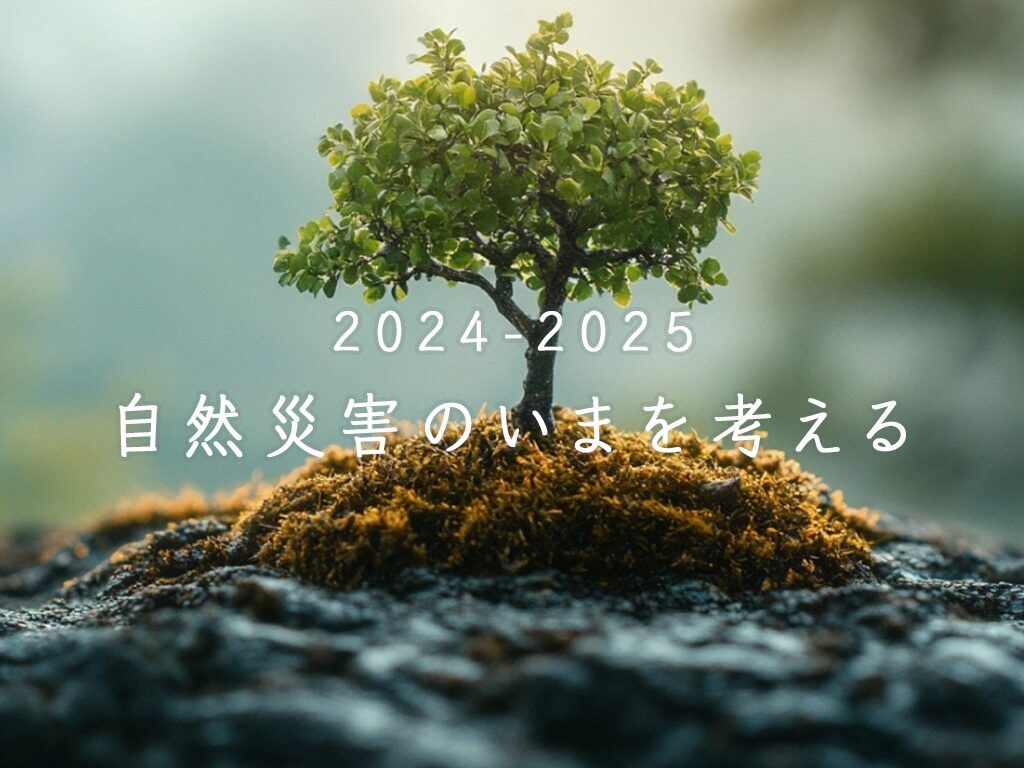2024年から2025年にかけて、世界は記録的な自然災害に見舞われています。
気候変動により全球気温が初めて1.5℃の閾値を突破し、従来の「100年に一度」とされていた災害が日常的に発生する新たな時代に突入しました。
2024年には383起の重大災害事件が記録され、風暴と洪水が全体の75%以上を占めています。
そして2025年に入っても、テキサス州洪水災害で137人が犠牲になるなど、深刻な災害が続いています。
これらの災害は単発の出来事ではなく、現在も多くの被災地で復興が続いており、継続的な支援が必要な状況です。
今回は、現在進行形で影響が広がる主要災害の現状と、寄付による支援がどのように被災地の復興と将来の災害対策に貢献できるかを詳しく解説します。
第1章:現在も続く主要災害の影響
能登半島地震:1年半経っても続く復興への道のり
2024年1月1日に発生した能登半島地震(マグニチュード7.6)は、2025年8月現在も深刻な影響を与え続けています。死者数は504人に達し、約15万棟の建物が損壊しました。
最も深刻なのは復興の遅れです。地震から1年半が経過した現在も、多くの住民が仮設住宅での生活を余儀なくされています。
「大工さんも大忙しで予約できない」という状況が続き、住宅修復が思うように進んでいません。
さらに深刻なのは人口減少の加速です。輪島市、珠洲市等の重災区では人口の持続的減少が続いており、地域の持続可能性そのものが問われています。海底隆起により60の漁港が被害を受け、地域の基幹産業である漁業にも深刻な打撃を与えています。
しかし、希望の光も見えています。2025年8月には「能登半島地震復興支援チャリティーオークション第6弾」が実施され、継続的な資金調達が行われています。また、Wリーグサマーキャンプが石川県で開催されるなど、スポーツを通じた復興支援も活発に行われています。
モロッコ地震:山岳地帯での復興の困難
2023年9月に発生したモロッコ地震は、2025年現在も継続的な影響を与えています。
死者数2,900人以上という甚大な被害をもたらしたこの地震は、特に山岳地帯での復興の困難さを浮き彫りにしています。
山間部では建設資材の輸送が大きな課題となっており、住宅の再建が思うように進んでいません。一方で、被災地の女性たちが廃墟から新たな収入源を見つけ、コミュニティの復興を支える取り組みが注目されています。
国際支援も継続されており、日本は2025年7月に地震モニタリング機材の整備と、政府・地方自治体関係者への研修を通じた地震対応能力強化支援を実施しました。このような技術移転は、単なる復旧支援を超えて、将来の災害に対する備えを強化する重要な取り組みです。
フィリピン連続台風災害:累積的被害の深刻さ
2024年10月から11月にかけて、フィリピンでは約1ヶ月間で6つの台風が連続して襲来しました。この連続災害により160人以上が死亡し、約900万人が被災しています。
連続災害の最も深刻な問題は、復旧作業中の再被災です。
最初の台風で被害を受けた地域が復旧作業を進めている最中に次の台風が襲来するため、被害が累積的に拡大していきます。
2025年7月には新たにフィリピン洪水緊急支援が決定され、AMDA(アムダ)がフィリピン支部のメンバーを中心に被災地のニーズに基づいた支援を実施しています。また、フィリピンと米国による共同災害対応も行われており、国際的な連携による支援体制が構築されています。
2025年の新たな災害
2025年に入っても深刻な災害が続いています。7月4日にはテキサス州でグアダルーペ川が氾濫し、わずか2時間で水位が8.4メートル上昇、137人が犠牲になりました。
瑞士再保険集団の予測によると、2025年の全球自然災害保険損失は1500億ドルを超える可能性があります。北大西洋のハリケーンシーズンと火災シーズンが継続中で、上半期だけで既に大きな損失を記録しています。
Virginia Tech専門家は「全災種対応」戦略を提唱し、ハリケーンだけでなく雪崩、竜巻、洪水、山火事への包括的対応の必要性を指摘しています。
AIを活用した予測システムの新たな突破も期待されており、災害対応技術の進歩が注目されています。

第2章:寄付による支援の現状と効果
多様化する支援の形
現代の災害支援は、政府、国際機関、NGO、企業、そして個人寄付者など、多様なアクターによって支えられています。それぞれが異なる強みを持ち、相互に補完し合いながら包括的な支援体制を構築しています。
寄付による支援の最大の特徴は、迅速性と柔軟性にあります。政府や国際機関の支援には予算承認や手続きに時間がかかる場合がありますが、民間の寄付は災害発生直後から迅速に支援活動を開始することができます。
NGOによる専門的支援
設立25周年を迎えたジャパン・プラットフォーム(JPF)には現在47のNGOが加盟しており、それぞれがレスキュー、医療、水や食料などの専門分野で活動しています。
JPFの強みは、緊急時の迅速な対応力と、加盟NGOが連携して効率的な支援活動を展開できることです。
難民を助ける会(AAR Japan)は、能登半島地震発生から約1年半が経過した2025年8月現在も、在宅被災者への支援を継続しています。AARの調査によると、地震から1年半が経った今も家屋の修復が継続しており、将来に対する不安の声が聞かれています。
ワールド・ビジョン・ジャパンは、緊急援助、復興支援、防災・減災の三本柱で活動しており、緊急事態に備えて皆様からお預かりしている緊急援助募金が、速やかな支援の初動を可能にしています。
ADRA Japanは世界約120か国に支部を持つ世界最大規模のNGOで、「ひとつの命から世界を変える」をモットーに、紛争・災害被災地や途上国での支援活動を展開しています。
企業による戦略的支援
企業による災害支援も重要な役割を果たしています。ソニーは、グローバルな企業市民として、大規模な自然災害や地域紛争が発生した際に緊急人道支援活動を実施しています。
100%民間団体である「リブート珠洲」は、能登半島地震の被災地である石川県珠洲市で復興支援ツアーを通じて地域の復興と発展に貢献しています。
企業寄付による社会貢献を実現する仕組みを提供し、民間セクターの力を復興に活用しています。
企業による災害支援の特徴は、資金提供だけでなく、企業の持つ技術やノウハウを活用した支援が可能な点です。通信企業による緊急通信インフラの提供、物流企業による支援物資の輸送、IT企業による情報システムの構築などが効果的な支援となっています。
クラウドファンディングの新しい可能性
近年、クラウドファンディングを活用した災害支援が注目を集めています。2025年8月には、アフガニスタン生計支援クラウドファンディングが目標を達成し、多くの方の温かいご支援により無事に目標を達成することができました。
「For Good」は、”社会をより良くしたい”という想いを誰でもアクションに変えられる、ソーシャルグッドに特化したクラウドファンディングプラットフォームです。
掲載手数料0%・達成率No.1という特徴を持ち、社会課題解決に特化したプロジェクトを支援しています。
クラウドファンディングの利点は、小額からの参加が可能で、多くの人が支援に参加できることです。また、プロジェクトの透明性が高く、寄付者が支援の使途や成果を明確に把握できます。
ウガンダ難民支援では、RICCI EVERYDAYがブランド創業10周年の新たな挑戦として、難民の自立とウガンダ社会の持続的安定化を図るクラウドファンディングを開始しています。
国際協力機構(JICA)による技術移転
JICAは、日本の防災技術と経験を世界に展開する重要な役割を果たしています。トルコに対しては、2023年2月に発生した大地震を受けて、建物の地震対策に関する長年にわたる協力を継続しています。
日本が長年にわたり蓄積してきた知識や技術を共有することで、他国の防災能力向上に貢献しています。
これは、単なる支援を超えて、将来の災害被害を予防する効果的な投資と言えます。
JICAの支援は、単発の技術提供ではなく、現地の能力強化を重視しています。
モロッコに対しては、地震モニタリングに必要な機材等の整備だけでなく、政府・地方自治体関係者やコミュニティーに対する研修を通じた地震対応能力強化等の支援を行っています。
災害ボランティアネットワークの進化
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)は、東日本大震災の教訓から2016年に設立されました。
災害時に支援の「もれ・むら」を防ぎ、地域や分野を超えた連携を推進することを目的としています。
JVOADは、熊本地震、九州北部豪雨などでの連携推進の実績を持ち、災害対応における調整機能の重要性を実証しています。
複数の支援団体が効率的に連携することで、支援の重複を避け、より多くの被災者に適切な支援を届けることが可能になります。
災害ボランティア活動も、年々専門性が向上しています。
CWS Japanのように、エンジニアとして異国の自然災害に向き合う専門的な支援を行う団体も登場しています。このような専門性の向上は、災害支援の効果を大幅に向上させています。

第3章:気候変動時代の災害対策と寄付の役割
1.5℃上昇時代への適応
世界気象機関(WMO)が2025年5月に発表した「2025-2029年の気候予測」は、衝撃的な内容でした。今後5年間のうち少なくとも1年が再び1.5℃を超える確率は86%とされ、5年平均で1.5℃を超える可能性も70%に達しています。
この予測は、従来の災害対策の前提を根本的に変える必要性を示しています。
「日本の気候変動2025」では、新たに日本南方海域の海洋中の溶存酸素量の長期変化傾向が掲載され、海洋環境の変化が陸上の気象にも大きな影響を与えることが明らかになっています。
日本の平均気温は世界より速い速度で上昇しており、異常気象はもはや一過性の自然災害だけでは済まされない状況となっています。
これまでの「100年に一度」の災害が「10年に一度」、さらには「毎年」発生する可能性が高まっています。
国際司法裁判所の勧告と法的義務
2025年7月、国連の司法機関である国際司法裁判所(ICJ)が、気候変動対策について世界各国は国際法上、「あらゆる措置をとる義務がある」とする勧告的意見を初めて出しました。
この勧告は法的拘束力を持ちませんが、各国や企業に対して気候変動対策の強化を求める重要な指針となっています。
この勧告は、災害対策を単なる事後対応から、事前の予防策へとシフトさせる必要性を法的な観点からも裏付けています。気候変動の緩和と適応の両方において、国際的な協力と民間セクターの参画が不可欠となっています。
防災・減災対策の強化戦略
気候変動により極端気象の予測がより困難になる中、早期警戒システムの高度化が急務となっています。従来の気象観測に加えて、AI・IoTを活用した予測システムの導入が進んでいます。
日本では、気象庁が「油断せず身の安全確保を 少ない雨でも危険度高まる」という警告を発しており、従来の経験則では対応できない新しいタイプの災害への備えが必要となっています。
寄付による支援においても、緊急支援だけでなく、このような予防的な技術開発への投資が重要になっています。民間の技術力と資金を活用することで、より効果的で革新的な早期警戒システムの開発が可能になります。
建築基準と都市計画の見直し
能登半島地震やモロッコ地震の事例が示すように、建物の耐震性向上は人命保護の最も基本的な要素です。
JICAがトルコに対して実施している建物の地震対策技術協力は、日本の長年の経験と技術を活用した効果的な支援事例です。
しかし、技術移転だけでは不十分で、現地の経済状況や文化に適応した建築基準の策定が必要です。寄付による支援は、このような技術移転と現地適応の橋渡し役として重要な機能を果たすことができます。
地域レジリエンスの構築
災害に強い地域づくりには、ハード面の整備だけでなく、ソフト面での地域レジリエンス(回復力)の構築が不可欠です。
能登半島地震の復興過程で見られるように、地域コミュニティの結束力と自立性が復興の速度を大きく左右します。
地域レジリエンスの構築には、社会関係資本の強化、経済基盤の多様化、知識と技能の蓄積、制度的基盤の整備が重要です。これらの要素は、寄付による支援を通じて効果的に強化することができます。
技術革新の活用
民間企業の技術革新は、災害対応の効率性と効果を大幅に向上させる可能性を秘めています。
特に、AI・機械学習による災害予測と被害評価の精度向上、ドローン・ロボット技術による危険地域での救助活動、衛星技術によるリアルタイムでの被害把握、通信技術による災害時の通信インフラ確保などの分野での技術革新が期待されています。
これらの技術開発には多額の投資が必要であり、政府の研究開発予算だけでは限界があります。民間からの寄付や投資を活用することで、より迅速で効果的な技術開発が可能になります。
国際協力体制の強化
日本の防災技術と経験は国際的に高く評価されており、多くの国から技術移転の要請があります。
しかし、効果的な技術移転には、単なる技術の提供を超えて、現地の文化や社会構造に適応したアプローチが必要です。
東京大学の研究によると、日本が率先して国際的に通用する適切な災害リスク評価手法を提案し、これを国際スタンダードとして普及させることが重要とされています。これにより、日本を含む世界各地の災害に対するリスクを正しく評価できるようになります。
国際スタンダードの確立には、政府間の協力だけでなく、学術機関、NGO、民間企業の参画が不可欠です。寄付による支援は、このような多様なステークホルダーの参画を促進する重要な役割を果たすことができます。

まとめ:寄付で築く災害に強い未来社会
災害支援の新たなパラダイム
2024年から2025年にかけての災害を振り返ると、従来の災害対応の枠組みでは対応しきれない新しい課題が浮き彫りになりました。
気候変動により1.5℃の閾値を突破した地球では、「100年に一度」の災害が日常的に発生し、複合災害や長期化する復興が新常態となっています。
このような状況において、政府や国際機関だけでは限界があることが明らかになりました。
能登半島地震の復興遅延、モロッコ地震の継続的影響、フィリピンの連続台風災害が示すように、現代の災害は規模と複雑さにおいて、従来の対応能力を超えています。
寄付による支援の独自価値
寄付による災害支援には、迅速性、柔軟性、継続性、専門性、参加性という独自価値があります。災害発生直後から複雑な手続きを経ることなく支援を開始でき、政府の支援が届きにくい分野や地域に対しても柔軟に対応できます。
緊急期から復興期まで、段階に応じて支援内容を変更しながら長期間継続でき、各分野の専門NGOを通じて高度に専門化された支援を提供できます。
また、多くの人々が支援に参加する機会を提供し、社会全体の連帯感を高めます。
技術革新との融合
デジタル技術の進歩は、寄付による災害支援の効果を大幅に向上させています。ブロックチェーン技術による透明性確保、AIによる最適配分、モバイル技術による直接支援など、技術革新により支援の質と効率が向上しています。
データ駆動型支援により、より科学的で効果的な支援が可能になっています。予測分析、リアルタイム分析、学習システムの活用により、支援の精度と効果が継続的に改善されています。
持続可能な社会への投資
寄付による災害支援は、単なる事後対応を超えて、持続可能な社会への投資としての意味を持ちます。防災・減災への投資、早期警戒システムの構築、地域レジリエンスの強化など、将来の災害を予防する取り組みに対する投資が重要です。
世界銀行の研究が示すように、防災投資1ドルあたり4-7ドルの経済効果があることを考えると、寄付による防災投資は極めて効率的な社会投資と言えます。
個人から始まる社会変革
重要なのは、この大きな社会変革が個人の小さな行動から始まることです。月額1,000円の寄付でも、継続することで年間12,000円の支援となり、多くの人が参加することで大きな社会的インパクトを生み出します。
現在の災害支援活動は、次世代により良い世界を残すための責任でもあります。気候変動により災害リスクが増大する中、今の行動が将来の社会の安全と持続可能性を決定します。
行動への呼びかけ
この記事を読んでいる皆さんも、今すぐ災害支援に参加することができます。月額寄付制度への参加、クラウドファンディングでの支援、地域での防災活動への参加など、様々な方法があります。
重要なのは、完璧を目指すことではなく、小さくても継続的な行動を起こすことです。あなたの一歩が、災害に苦しむ人々への支援となり、より良い社会の実現につながります。
2024年から2025年の災害が教えてくれたのは、私たちが直面している課題の深刻さと、同時に人々の連帯と支援の力の大きさです。寄付による支援を通じて、私たちは災害に強い、より公正で持続可能な社会を築くことができます。
その第一歩を、今日から始めませんか。