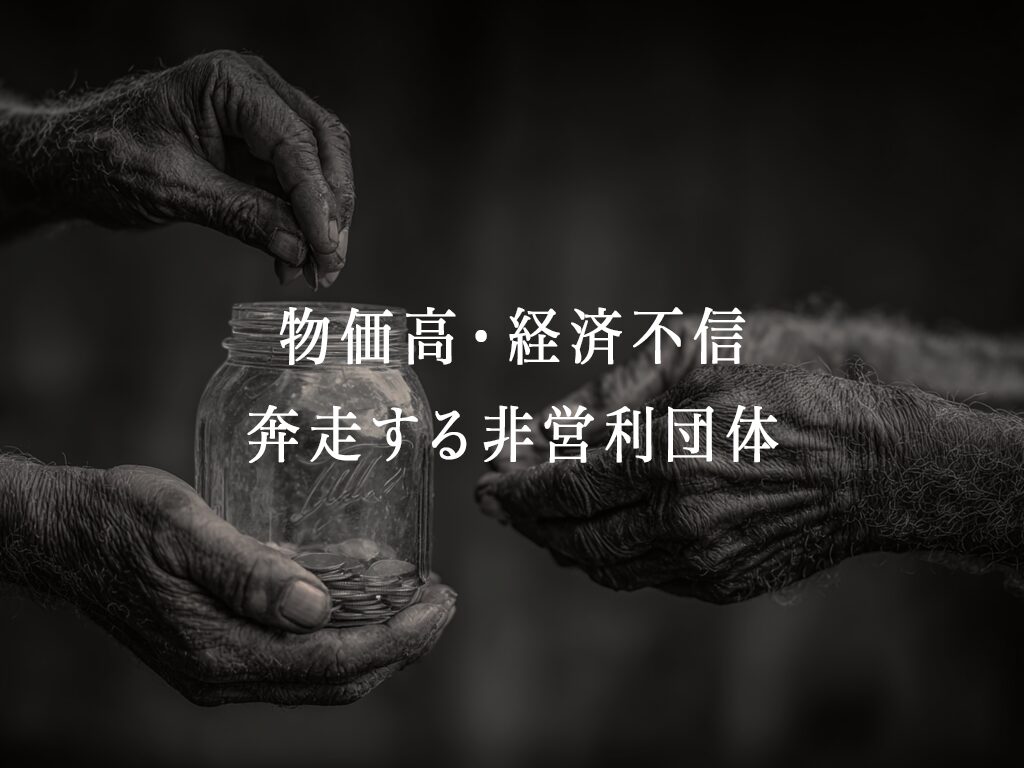目次
物価高と経済不信が突きつける“見えにくい貧困”
2025年4月の日本のヘッドラインCPI(消費者物価指数)は前年比+3.6%に達し、これが15カ月連続で2%台を上回る水準となっています。
東京都でも同月のコアCPI(生鮮食品を除く指数)は+3.4%、食料価格の上昇が主な押し上げ要因となっています 。
こうした異例の高物価の背景には、食料やエネルギー価格の高騰だけでなく、燃料補助金の縮小と賃上げの遅れが重なった結果、家計の実質的負担が増大していることが挙げられます。
しかし、公的支援の受け皿から漏れた人たち、例えばフリーランスや非正規雇用、ひとり親世帯、高齢単身者などは、こうした影響を人知れず受け止めています。その影で「見えにくい貧困」が深刻化し、社会の広がる支援の必要性が高まっています。
第1章:データで見る生活困窮のリアル——静かに広がる苦境
フードバンクの窮状
NPO法人フードバンク仙台が2024年7月に実施した全国調査では、66団体中63.6%が「寄付が減少した」と回答し、82.9%が「活動に支障が出ている」と答えています。
特に主食である米の寄付は全体の68.2%の団体で減少。全国的に食料備蓄の枯渇が深刻です。
フードバンク仙台では報告者から、「電気・ガスが止まり、2週間ほど何も食べられなかった」といった緊急事態の声も上がっています。
ひとり親家庭への影響
認定NPO法人グッドネーバーズによる「グッドごはん」プロジェクトの最新報告では、利用者の約50%が年収200万円以下、さらに約90%が主要食材を買うのが困難と回答しています 。物価高の中で月1万円分の食材提供すら不足する状況です。
生活保護世帯の苦境
公的支援の代表である生活保護受給者世帯も、物価上昇に追いつけず実質購買力が低下しています。2025年度の生活扶助基準の見直し議論が焦点となる一方で、受給者からは「支援が足りない」との声が相次いでいます。

第2章:支援に立ち上がるNPO・非営利団体の取り組み
フードバンク仙台の現場対応
フードバンク仙台の活動報告によると、2024年度は述べ約7,100人に食料を提供し、累計で約77万食に達しました。とりわけ2023年度以降の物価高が顕著であるため、過去最多の支援件数を記録しています。
地域では、電気・ガスが止まり、数日間食事を十分にとれない世帯や、貯金が底をつく家庭への緊急支援も実施されています。
また、高齢者の一部が携帯電話未納による連絡断絶と仕事停止に至るなど、社会的孤立の兆候も報告されています。
こうした実態を受け、同団体は野菜自家栽培(じゃがいも・玉ねぎ)を2023年度から開始。2024年度には1.5トン以上を収穫・配布し、地域農家やボランティアと連携しながら活動を継続しています。
グッドごはん(ひとり親家庭向け支援)
「グッドごはん」を運営するグッドネーバーズ・ジャパンの最新調査では、利用者の約50%が年収200万円未満、そして約90%が食材の購入に困難を抱えています。
さらに、2025年6月に実施されたアンケートでは、学校給食のない長期休みに約90%が「子どもへの栄養バランス保持が難しい」と回答。回答者の多くが自身の食事を削り、子どもが1日2食以下に減らすケースも報告されています。
利用者には、「光熱費や食品価格の高騰で、久しぶりにしっかり食事をさせることができた」「子どもに安心感を与えられた」といった温かい声が届いています 。
第3章:背景にある構造的要因とは?
家計を圧迫する“三大コストの上昇”
統計によれば、物価高は食料品だけでなく、光熱費や交通費にも影響が波及しており、生活困窮層への圧迫が加速しています。これらが複合化することで、食費へ割ける予算が削られる“二重・三重苦”の構造が生じています。
非正規雇用と実質賃金の伸び悩み
非正規労働者の賃金は上がらず、物価上昇に見合った収入増が実現できていません。
ワーキングプアの拡大に伴い、「働いても生活が厳しい」という、家計の限界を超える事態が続いています。
第4章:私たちにできる“小さな支援”の提案
モノの寄付・フードドライブへの参加
地域開催のフードドライブは、フードバンクの備蓄不足を補う重要な支援になります。ご家庭に眠る常温保存できる食品、缶詰、乾麺などをぜひ活用してみてください。
小口寄付・クラウドファンディング支援
“グッドごはん”などでは、1人あたり1,000円から継続寄付を受け付けています。
月1,000円の支援は、1世帯分の食品提供につながる貴重な資源となります。
情報拡散と周囲への声かけ
SNSやコミュニティ、企業に支援活動の必要性を伝えることも大切な支援です。「フードバンクが必要としている」「寄付が減っている」といった事実を発信するだけでも、支援の輪が広がります。
結語:物価高を“チャンス”に変える支援社会へ
物価高と経済不安が人々の日常を押しつぶす中、“つながる支援” を通じて、社会はまだ優しさと連帯を失っていません。
一人ひとりの行動—「食材1つの寄付」「声をかける一言」「情報を発信する力」—が、困窮層の命と心を支える大切な支柱になります。
FIRST DONATEは今後も、小さな一歩が重なって大きな社会の変革につながることを信じ、支援の最前線に立ち続けます。あなたの一歩が、明日の誰かの安心に変わることを願っています。