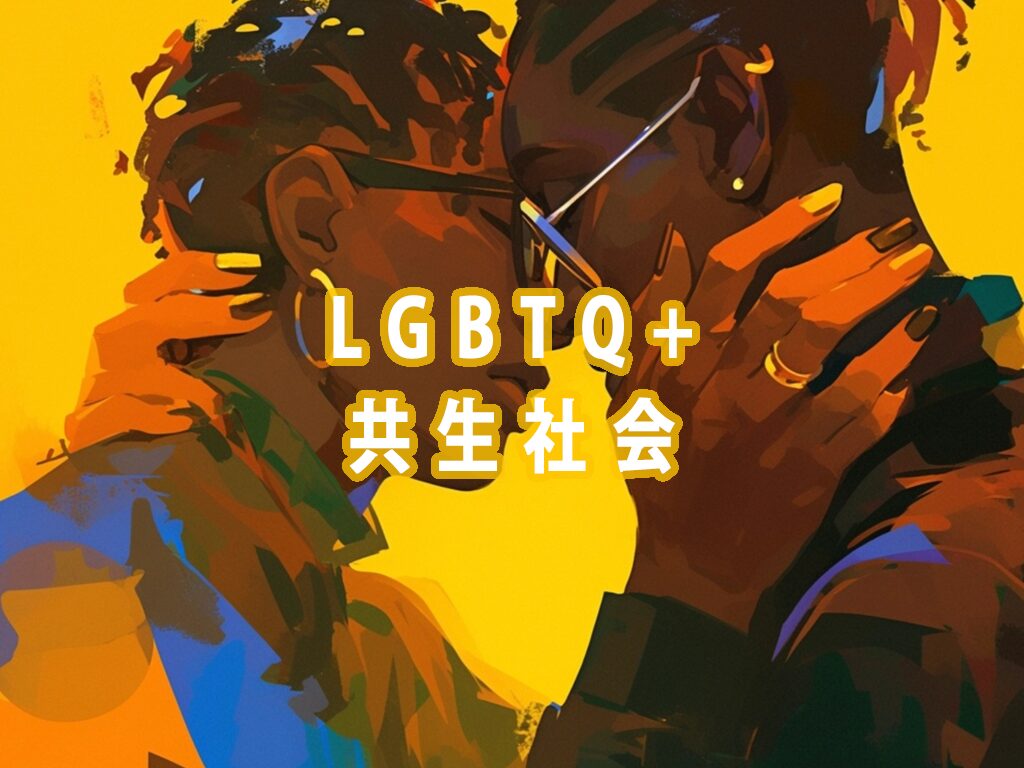目次
1. 日本および世界のLGBTQ+をめぐる現状と課題
日本では近年、テレビやネットでLGBTQ+に関する話題を目にする機会が増え、理解が進んできたようにも見えます。
しかし、当事者が直面する差別や孤立は依然として深刻です。ある調査では、性的少数者の約6割が学校でいじめを経験したとされ、特に40代では65%もの人が学生時代にいじめを受けたと答えています。
トランスジェンダーの58%が自殺念慮を抱えたことがあるという報告もあり、幼い頃から偏見にさらされ安心できる居場所を見つけられない現状が浮かび上がります。
また、約72%もの人が職場や学校でLGBTQ+への差別的な発言を聞いたことがあるとの調査結果もあり、日常生活の中に無意識の偏見が残っていることが分かります。
法制度の面でも、日本は課題を抱えています。例えば同性婚は2025年現在、日本では法的に認められていません。G7諸国では日本だけが同性カップルの結婚を保障しておらず、世界に目を向けると既に38の国と地域で同性婚が合法化されています
その一方で、まだ約60か国では同性同士の関係が法律で禁止されているなど、国によって状況は様々です。
日本国内では同性パートナーシップ証明制度が自治体レベルで広がり、2023年時点で全都道府県を含む300以上の自治体が導入しました。それでも法的な効力は限定的で、同性カップルはなお相続や医療同意など多くの権利を持てません。
また、性的指向や性自認を理由とする差別を明確に禁じる差別禁止法も存在せず、職場での解雇や住宅の入居拒否などに法的救済が及ばない可能性もあります。法律の不備は社会の無理解を助長しかねず、これも当事者の生きづらさにつながっています。
さらに、日本では「自分のことを相談できる相手が身近にいない」と感じて孤立するLGBTQ+当事者も少なくありません。
カミングアウト(自分の性的指向や性自認を打ち明けること)に踏み切れず、家族や友人から理解されない恐れから孤独を深めてしまうケースもあります。その結果、精神的なストレスを抱え込んでしまったり、不登校や離職、自傷行為などにつながるリスクも指摘されています。
特に10代の若者や高齢の当事者にとって、自分らしさを安心して語れる居場所やコミュニティの不足は大きな課題です。

2. 日本で進む法改正と社会的議論の動向
こうした状況を受け、日本でも近年はLGBTQ+に関する法整備や議論が活発化しています。2023年6月には、自民党を中心に「LGBT理解増進法」が成立しました。
この法律は「全ての国民が等しく基本的人権を享有し尊重される」「不当な差別的取扱いは許されない」といった理念を掲げ、国や地方自治体に対して性的マイノリティへの理解促進施策を求める内容となっています
しかし、差別を直接禁止する明確な規定がなく、保守派への配慮から「女性が安心できる環境に留意する」との一文が盛り込まれたため、「かえって差別を正当化する恐れがある」との批判も少なくありません
実際、この法律成立前後の国会審議では賛否両論が戦わされ、社会的な関心の高さが浮き彫りになりました。法律は一歩前進ではあるものの、当事者を守る実効性については引き続き監視と改善が必要です。
一方で、同性婚の実現に向けた動きも進んでいます。
日本では2019年以降、各地で同性婚を求める訴訟(いわゆる「結婚の自由をすべての人に」訴訟)が提起されました。
2021年3月の札幌地裁判決で「同性婚を認めない現行法は違憲状態」との判断が示されると、大きな話題となりました。その後も各地の裁判所で判断が分かれていますが、2023年5月の名古屋地裁では違憲と認める画期的な判決が出ています。
世論も同性婚を支持する声が多数派となっており、2023年の国際調査では日本で74%もの人が同性婚に賛同すると回答しました(「強く賛同」が17%、「どちらかといえば賛同」が57%)。
これは同性婚が未承認の国としては最も高い水準で、既に同性婚が法制化されている米国(63%)や英国(73%)よりも高い結果でした。世論の後押しを受け、与野党の一部議員も超党派で婚姻平等(同性婚合法化)に向けた法案提出を模索しており、今後の国会論議が注目されています。
また、社会全体の意識も変化してきています。
企業ではLGBTQ+に配慮した職場づくりが広がり、同性パートナーに社内福利厚生を提供する企業や、トランスジェンダー社員の制服選択を自由化する企業も増えました。
教育現場でも2015年に文部科学省が全学校に向けて性的少数者の児童生徒への配慮を求める通知を出し、教科書に多様な性の記述が登場するなど変化が始まっています。
大学の入試要項でトランスジェンダー学生への対応を明記する例もあります。毎年春には東京や大阪をはじめ各地でプライドパレード(虹色の旗を掲げて多様性を祝福する行進)が開催され、企業や自治体も参加して盛大に行われるようになりました。
2022年には愛知県や茨城県など地方で初めて大規模プライドイベントが開かれるなど、支援と理解の輪は全国に広がりつつあります。
一方で依然として一部の政治家による差別的な発言や、SNS上での誹謗中傷も見受けられ、課題も残っています。それでも、「誰もが自分らしく生きられる社会」を目指す前向きな動きが着実に力を増してきていることは希望と言えるでしょう。

3. 寄付で支えられるLGBTQ+支援と主な団体の活動
LGBTQ+当事者を取り巻く問題に対して、私たちにも寄付という形で支援できることがたくさんあります。
ここでは日本で信頼できる支援活動を行う主な団体とその取り組みをご紹介します。それぞれの団体が寄付に支えられて運営されており、寄付金の使い道やその成果も具体的に公開されています。自分の想いに合った団体を見つけ、ぜひ応援の輪に加わってみてください。
3.1 認定NPO法人 ReBit(リビット) – すべての子どもがありのままで大人になれる社会を目指して
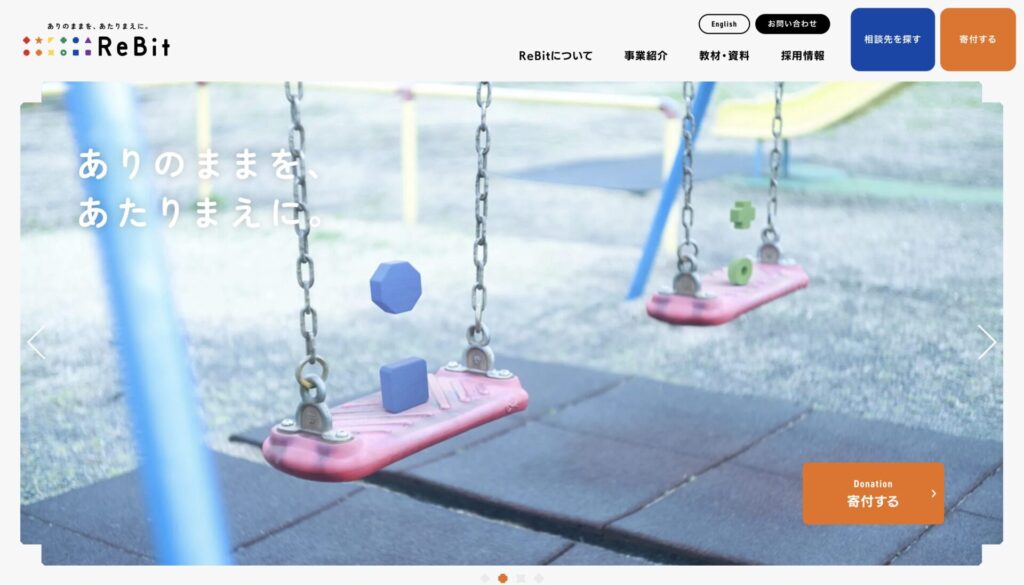
ReBitは、LGBTQ+を含む全ての子どもたちが「自分らしい未来」を描ける社会を実現しようと、2014年に設立された団体です。
主な活動は、小中高校や教育委員会などに出向いて行う学校での出張授業や教材の提供、そして企業や行政への研修プログラムです。講師はLGBTQ+当事者を含むスタッフが務め、正しい知識と多様な生き方のロールモデルを子どもたちに届けています。
さらに、就職活動や職場で悩む若者を支援するキャリア相談、毎年全国で開催されるLGBT成人式(20歳を迎えるLGBTQ当事者を祝うイベント)なども手がけ、教育から社会参加まで幅広く若年層をサポートしています。
寄付金は、これら授業の開催費用や教材開発、相談事業の運営などに活用されています。例えばReBitでは月1,000円からのマンスリーサポーター制度「にじいろバトン」を募集中で、継続寄付により小学校の1クラス分に相当する子どもたちへ授業を届けたり、就活生への個別支援を提供したりすることができます。
実際、支援や寄付のおかげで日本初のLGBTQフレンドリーな就労支援センター「ダイバーシティキャリアセンター」を2021年に東京・渋谷に開設し、開所以来全国から延べ6,000件以上の相談に対応することができました
寄付が具体的に形となり、多くの若者の背中を押している好例です。
「学校でReBitの授業を受けて、自分は一人じゃないと思えた」という当事者の声も寄せられており、寄付による支援が子どもたちの自己肯定感を高める大きな力になっています。
3.2 認定NPO法人 虹色ダイバーシティ – 誰もが働きやすい職場づくりと法制度改善を推進

認定NPO法人 虹色ダイバーシティ
虹色ダイバーシティは、大阪に拠点を置き職場環境の整備や調査研究・政策提言を通じてLGBTQ+が生き生きと働ける社会を目指す団体です。
2013年の設立以来、企業や自治体向けの研修・コンサルティング、人事制度の整備支援、そして国内初の大規模実態調査「LGBTと職場に関するアンケート」を継続的に実施してきました
その調査データを基に、職場で何が課題かを可視化し、企業にダイバーシティ施策を促す働きかけを行っています。また、「職場のLGBT読本」などの書籍出版や情報発信にも注力し、社会全体の意識改革に貢献しています。
近年では、行政や他団体との連携プロジェクトも積極的に展開しています。
大阪市淀川区と協働した地域の支援事業や、2025年には大阪に常設の「プライドセンター大阪」(LGBTQコミュニティセンター)を開設する計画も進行中です。プライドセンター大阪は、虹色ダイバーシティが中心となって進めているプロジェクトで、居場所提供や相談対応を行う拠点として期待されています
同団体への寄付は、こうしたセンターの運営資金や調査研究の費用に充てられます。例えば2021年には休眠預金等活用制度の公募に採択され、寄付者からの資金と合わせてコミュニティセンター事業に充当しました
虹色ダイバーシティの活動は、信頼できるデータを社会に示し企業や政府を動かすことで、制度面の遅れを埋め、働く人々が安心できる環境づくりにつなげている点が大きな特徴です。
寄付によって支えられたその取り組みは、「誰ひとり取り残さない」職場と社会の実現に向けて確かな一歩を踏み出しています。
3.3 認定NPO法人 グッド・エイジング・エールズ – セクシュアリティの枠を超えてエールを送り合える社会へ

グッド・エイジング・エールズ(Good Aging Yells)は、「LGBTもそうでない人も共に楽しめる場を作る」ことをモットーに2010年に発足した団体です
名前には「誰もが年を重ねても自分らしく豊かに生きていけるようエール(応援)を送ろう」という想いが込められています。カフェやイベント、シェアハウス作りなど様々なプロジェクトを通じて、セクシュアリティの違いを超えて人々が交流できるコミュニティづくりに取り組んでいます
この団体が手がける代表的なプロジェクトの一つが「プライドハウス東京」です。
プライドハウス東京は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを契機に設置された常設の総合LGBTQセンターで、情報発信や相談対応、イベント開催などを行う安心・安全な居場所です
グッド・エイジング・エールズは他団体や企業と連携し、このセンターの開設と運営に中心的な役割を果たしました。
2020年10月、東京・新宿にオープンした「プライドハウス東京レガシー」は日本初の恒久的なLGBTQ支援センターであり、図書室に600冊の関連書籍を備え、相談や交流の場を無料で提供しています
この開設にはReadyforでのクラウドファンディングなど多くの寄付が寄せられ、まさに寄付の力で実現した施設と言えます。現在も運営費の一部は寄付や助成金でまかなわれており、例えば休眠預金を活用した助成事業にも採択されるなど
持続可能な資金確保に努めています。
グッド・エイジング・エールズは他にも、著名写真家と協力した「OUT IN JAPAN」という大型フォトプロジェクトを展開し、全国のLGBTQ当事者のポートレート写真を撮影・公開して世間に多様な姿を可視化する活動や、LGBTQフレンドリーな高齢者住宅のあり方を模索するプロジェクトなども行っています
寄付金はこうしたイベントやプロジェクトの運営費、広報費、人件費などに使われ、常に新しい試みを生み出す原動力となっています。
「誰もが自分の夢を描ける社会は、あなたの力があってこそ」というメッセージを掲げ、寄付募集にも積極的です。グッド・エイジング・エールズへの支援は、コミュニティの現場から社会を変えていくユニークなアプローチを後押しし、未来のシニア世代まで見据えた共生社会づくりにつながっています。
3.4 NPO法人 LGBTの家族と友人をつなぐ会 – 周囲の理解と受容を広げるアライ支援ネットワーク
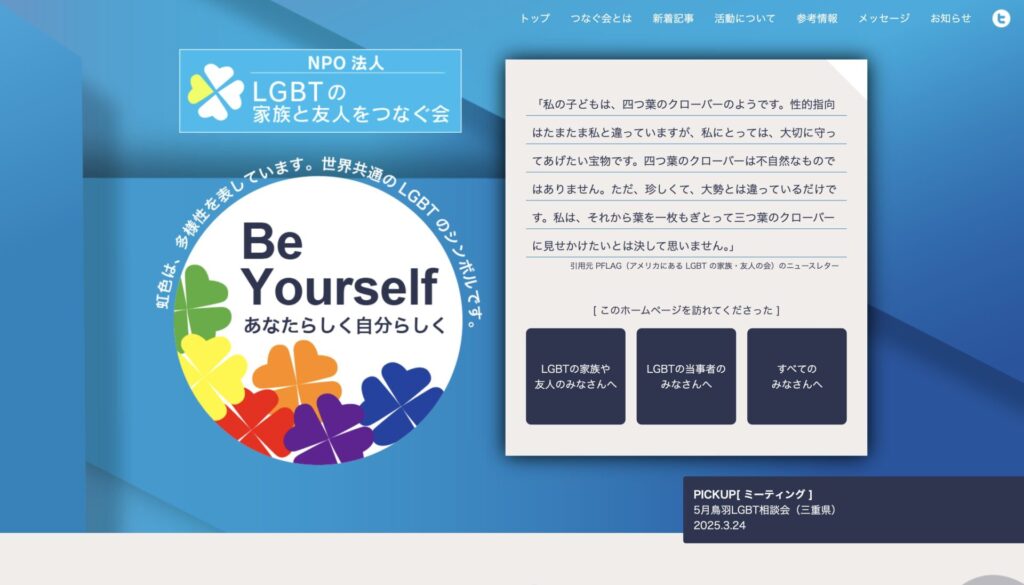
「LGBTの家族と友人をつなぐ会」は、その名の通り当事者の家族や友人(=アライ)が集い、性の多様性への理解を深め合う活動を行う団体です。
2013年に兵庫県で設立され、現在では東京、愛知、福岡、大分など全国各地にメンバーが広がっています。身近な家族や友人が正しい知識を持ち、当事者を受け入れ支えることができるようになること、そして社会全体から偏見や差別をなくすことを目的に掲げています。
具体的な活動としては、各地で定期的に交流会や勉強会を開催しています。
そこでは当事者の家族同士が悩みを共有したり、専門家を招いてLGBTQ+やSOGIE(性的指向・性自認)について学んだりしています。当事者本人も参加でき、自身のカミングアウトの経験を話したり、家族の本音を聞いたりすることで相互理解を深める場にもなっています。
また、地域のプライドイベント(例:名古屋レインボープライド等)にブースを出展し、一般の来場者に向けて家族の立場から多様性を訴える啓発活動も行っています。
この会の特徴は、「周囲の人」が変わることで当事者の生きやすさを支えるというアプローチです。
寄付金は主に交流会の運営費(会場代や資料印刷代)、広報活動費(パンフレット作成やウェブサイト維持)などに充てられています。小規模な団体ではありますが、家族や友人だからこそ届けられるメッセージは大きな説得力を持ちます。実際、参加者からは「自分の子どもを理解してあげられず悩んでいたが、他の親御さんの話を聞いて前向きになれた」「家族が勉強会に参加してくれたおかげでカミングアウト後の関係が改善した」といった声が寄せられています。
寄付という形でこの会を支えることは、当事者の最も身近な環境をあたたかく変えていくことにつながります。身内の理解者(アライ)が増えることは当事者にとって大きな希望となり、安心して暮らせる社会の土台作りになるのです。
3.5 NPO法人 アカー(OCCUR) – 相談支援と人権擁護を続ける草分け的存在

アカー(OCCUR、「動くゲイとレズビアンの会」)は、1986年に結成された日本のLGBTQ+支援団体の草分け的存在です。
30年以上にわたり、社会の偏見と闘いながら当事者の相談相手となり、行政への提言や国際交流を続けてきました。その活動は多岐にわたり、レズビアンとゲイのための電話相談や、HIV/エイズに関する情報提供ラインの運営、弁護士による法律相談会など、当事者が直面する様々な悩みに対応しています。
まだ今ほど理解が進んでいなかった時代から地道に続けてきた相談事業は、孤独を抱える多くの人々の命綱となってきました。
また、アカーは啓発イベントの開催や人権擁護活動、政策提言、海外の団体との協力などにも尽力しています。
1980~90年代には同性カップルの宿泊拒否事件に対して法的闘争を支援し、社会に波紋を投じました。毎年12月1日の世界エイズデーには啓発イベントを実施するなど、HIV/エイズとLGBTQ+に関する正しい知識普及にも努めています。
当事者コミュニティ内のネットワーク作りにも積極的で、他のNPOや支援者と連携しながら活動の輪を広げています。
アカーの運営は会員のボランティアと寄付によって支えられています。
寄付金は、相談電話の維持費やイベント開催費、機関紙の発行などに使われています。電話相談では専門の相談員が丁寧に耳を傾け、必要に応じて医療機関や法的支援につなぐなどのサポートを行っています。
こうした地道な取り組みは派手さこそありませんが、「話せる相手がいる」と思えるだけで救われる人も多く、その意義は計り知れません。
長年の活動によって培われた信頼は厚く、行政機関や国際団体からの情報提供依頼を受けることもあります。寄付によってアカーの活動を支えることは、最も困っている人に寄り添う手を差し伸べ続けることにつながります。草の根の支援が社会全体の優しさを底上げし、誰もが声を上げられる土壌を守っているのです。

4. 支援の新しい形と寄付による変化
日本におけるLGBTQ+支援は、この数年で大きな変化と前進を遂げています。
寄付のあり方も多様化し、クラウドファンディングの活用や企業・行政との協働、オンラインでの少額寄付など、新しいモデルが次々と登場しています。それに伴い、寄付が具体的に生み出した成果も見え始めてきました。
4.1 クラウドファンディングで広がる支援の輪
インターネットを通じて資金を募るクラウドファンディングは、LGBTQ+支援の分野でも重要な手法となっています。
先述したプライドハウス東京やReBitの事例のように、新しいプロジェクトの立ち上げ時には幅広い共感を集めて寄付を募ることで、大きな資金を短期間で集めることに成功しています。
ReadyforやCampfireといった国内主要プラットフォームでは、「LGBT」「多様性」をキーワードにしたプロジェクトが数多く公開され、書籍の制作やコミュニティセンター開設、地域イベントの開催資金など様々な目的で活用されています
実際、ある地方都市ではLGBTQの居場所づくりのためのクラウドファンディングが行われ、目標額を達成して交流スペースが開設されたケースもあります。
クラウドファンディングは支援者にとって使途が明確で参加意識が高まる点が魅力であり、SNSを通じた拡散によってそれまで関心のなかった層にもアプローチできるため、寄付文化の裾野拡大に大きく寄与しています。
4.2 企業CSR・行政との協働が生む新たな支援
近年、多くの企業がCSR(企業の社会的責任)活動の一環としてLGBTQ+支援に関与するようになりました。
例えば、大手企業が売上の一部をLGBTQ+団体に寄付するキャンペーンを展開したり、社員ボランティアがプライドパレードの運営を手伝ったりといった動きが見られます。
Yahoo!ジャパンの「ネット募金」では、自社のポイント(TポイントやPayPayポイント)をLGBTQ+支援団体へ寄付できる仕組みを提供しており、手軽に参加できると好評です(教育支援分野では累計数億円の寄付実績があります)。また、自動車メーカーのアルファロメオが多様性支援のスポンサーとなるなど、業種を超えた企業の支援も広がっています。
行政との協働も支援を加速させています。東京都や大阪市では、NPOと連携して専門相談窓口を開設したり、コミュニティセンター事業に助成金を出したりする例が出てきました。
先述のプライドハウス東京レガシーも、国の休眠預金活用事業の助成を受けて運営されています。
2023年には東京マラソンの公式チャリティ先にグッド・エイジング・エールズが選ばれ、ランナーからの寄付がプライドハウス東京などの支援に充てられる試みも行われました。
行政・企業・市民がパートナーとなりリソースを出し合うことで、従来は実現が難しかった大規模プロジェクトが次々と動き出しています。
4.3 オンライン寄付と少額からの参加
インターネットの普及により、オンラインで気軽に寄付できる環境も整ってきました。
各団体の公式サイトからクレジットカードでワンクリック寄付ができるのはもちろん、最近では少額寄付を促す工夫も増えています。
たとえばキャッシュレス決済時に1円未満の端数を自動的に寄付するサービスや、買い物のおつりを募金に回せるスマホアプリなど、日常生活の中で負担なく寄付に参加できる仕組みが登場しています。
SNS上でも誕生日に寄付を募る「バースデードネーション」の呼びかけが広がり、友人の善意が連鎖して寄付につながるケースも増えてきました。
LGBTQ+支援においても、TwitterやInstagramで「#プライド月間に寄付」などと宣言して賛同者を募る動きが見られ、少額ずつでも支援する人が着実に増えています。
「自分の寄付は小さくても、たくさん集まれば大きな力になる」という意識が広まりつつあり、支援者数の増加そのものが社会の後押しとなって団体の信用力向上にもつながっています。
4.4 寄付が生み出すポジティブな変化
寄付による支援が積み重なった結果、少しずつではありますが目に見える変化も生まれています。
当事者コミュニティの間では、「寄付のおかげでこんなサービスが利用できるようになった」「支援を受けた自分が今度は支援する側になった」という声が聞かれるようになりました。
例えば、奨学金を受けたLGBTQ+の若者が社会人となり、寄付者として母校に恩返しするケースや、居場所支援を受けて救われた人が今度はボランティアスタッフとして活動に参加するといった支援の連鎖が生まれています。
寄付によって開設されたプライドセンターでは、「ここに来て初めて自分は一人じゃないと思えた」と利用者が涙ながらに語り、その様子を見たスタッフが改めて支援の意義を実感するというエピソードもありました。
寄付が単にお金の支援にとどまらず、人と人とのつながりや希望を生み出しているのです。
さらに、寄付文化の定着は社会全体の意識変革にもつながります。
多くの人がお財布や時間を少しずつ割いて支援活動に関わるようになると、LGBTQ+の課題が「自分ごと」として捉えられるようになります。
理解者・協力者が増えることで偏見や無関心が減り、やがては差別のない共生社会への推進力となっていくでしょう。
実際、寄付者が増えたことで団体の発信力が高まり、メディアで大きく取り上げられる機会が増えたり、行政への働きかけに説得力が増したりする効果も出ています。
寄付という形で支えられた活動が成功事例を積み重ねれば、「自分らしく生きていいんだ」という当事者の自信と、「私たちにもできることがあるんだ」という支援者の自信、その両方を社会にもたらすことになるのです。

5. 私たちにもできる支援:一人ひとりのアクションが社会を変える
最後に、共生社会の実現に向けて私たち一人ひとりができる具体的なアクションを考えてみましょう。
たとえ小さな一歩でも、それが積み重なれば大きな前進になります。「自分にも何かできることがある」と知ることが、希望ある未来への第一歩です。
5.1 信頼できる団体を見つけ継続的に寄付する
まずは、自分が共感できるミッションを持ち、信頼のおける団体を見つけてみましょう。
本記事で紹介したような実績ある団体は、ウェブサイトや報告書で活動内容や財務状況を公開しています。そうした情報を参考に、「ここを応援したい」という団体が見つかったら、できれば月々の継続寄付という形で支援を始めてみることをおすすめします。
継続寄付であれば一回あたりの負担は小さくても、1年・2年と続けるうちに支援総額は大きくなり、団体にとって安定した財源となります。
例えば「1日コーヒー1杯分(数百円)を寄付に振り向ける」と考えれば、無理なく続けやすいでしょう。
定期的に団体から送られてくるニュースレターやSNS投稿に目を通せば、自分の寄付がどんな風に役立っているか知ることもできます。そうして支援者自身が活動に関心を寄せ続けることで周囲にも自然と話題が広がり、寄付の輪がさらに大きくなる効果も期待できます。
5.2 少額・身近な方法から寄付を始める
「いきなり毎月はハードルが高い…」という方は、少額でもできる方法から気軽にチャレンジしてみましょう。
たとえば、通販サイトで貯まったポイントを寄付に充てたり、コンビニの募金箱におつりを入れたりといったことも立派な支援です。
最近はオンラインで「〇〇円から寄付できます」といったキャンペーンも多く、クラウドファンディングでも1,000円から支援可能なプロジェクトがたくさんあります。自分にできる範囲の金額で構いません。
一人ひとりの少額寄付が集まれば大きなインパクトになりますし、何より「支援者の数」が増えること自体が社会からの追い風となって団体の活動を後押しします。「まずはやってみる」ことで見えてくる景色もありますので、小さな一歩を踏み出してみましょう。
5.3 支援先を多様化し新しい仕組みを活用する
寄付先は一つに絞らず、関心に応じて分散させてみるのも良いでしょう。
例えば「教育現場の支援」と「職場環境の改善」の両方に関心があるなら、前者はReBitに、後者は虹色ダイバーシティに、といった具合に複数団体を応援できます。
それぞれ少額でも、合計すればあなたなりの寄付ポートフォリオができあがります。また、最近話題の遺贈寄付(自分の遺産の一部を寄付)や株式・暗号資産の寄付といった新しい方法もあります。
現役世代には馴染みが薄いかもしれませんが、大きな資産をお持ちの方が将来に託して寄付を行う例も増えてきました。
自治体の制度を活用する手もあります。
ふるさと納税の仕組みでLGBTQ+関連事業を支援している自治体もわずかですが出てきていますし、勤務先にマッチングギフト(社員の寄付額と同額を会社も寄付する制度)があれば利用してみましょう。
このように、自分に合った形で参加できる仕組みが今はたくさんあります。従来の枠にとらわれず柔軟に検討し、支援の幅を広げてみることも大切です。
5.4 周囲への発信とボランティア参加で支援の輪を広げる
寄付をしたらそれで終わりではなく、その体験や思いをぜひ周囲に発信してみてください。
例えば「こんな素敵な団体があるよ」と家族や友人に話してみたり、SNSで寄付先団体の活動報告をシェアしたりすることは、結果的に寄付文化を広めることにつながります。
あなたの発信を見聞きした人が初めて関心を持ち、新たな支援者が生まれるかもしれません。また、可能であれば現場のボランティアに参加してみるのも有意義です。
イベントスタッフや相談員の補助、クラウドファンディングの拡散協力など、団体によって募集しているボランティアは様々です。
時間という形での寄付とも言えるボランティア活動は、支援者自身が現場を知る貴重な機会にもなりますし、団体側に寄付者の生の声を届けることにもつながります。寄付者とボランティアの両方を経験することで支援のリアリティが増し、より長期的なコミットメントにもつながるでしょう。
少し想像してみてください。
あなたのその一歩が、誰かの人生を変えるかもしれません。
寄付によって運営される電話相談にかけた人が「生きていていいんだ」と思えたり、寄付で開催された交流会に参加した親御さんが「この子を理解しよう」と涙を流したり、寄付で設立されたセンターを訪れた若者が初めて笑顔になったり…。そんな瞬間を支えているのは、紛れもなく寄付という名の市民の力です。
おわりに:小さな一歩がつくる希望ある未来
少子高齢化が進む日本社会において、多様な背景を持つ人々が互いに支え合い、誰も排除されない共生社会を築くことはますます重要になっています。
その中でLGBTQ+への支援は、行政だけでは行き届かない領域を市民の力で補い、一人ひとりが自分らしく生きられる未来への投資でもあります。
幸いなことに、ここ数年で寄付に追い風となる制度改革や成功事例が次々と生まれ、企業・個人を問わず「支援したい」という意志を形にしやすい環境が整いつつあります。
例えば、ReBitの卒業生が今度は寄付者として次の世代を支えるように、支援の連鎖は少しずつ広がり始めています。
私たち一人ひとりも、自分のできる範囲で行動を起こすことで、その連鎖に加わることができます。
そしてその小さな一歩の積み重ねが、いずれ「誰もが自分らしく暮らせる社会」という大きな目標への推進力となるのです。
差別や孤立に苦しむ人がいない未来を思い描きながら、できることから始めてみませんか。
寄付という形で届けられるあなたのエール(応援)は、きっと誰かの勇気と笑顔に変わり、社会を優しく変えていくはずです。共に、希望ある未来への一歩を踏み出しましょう。