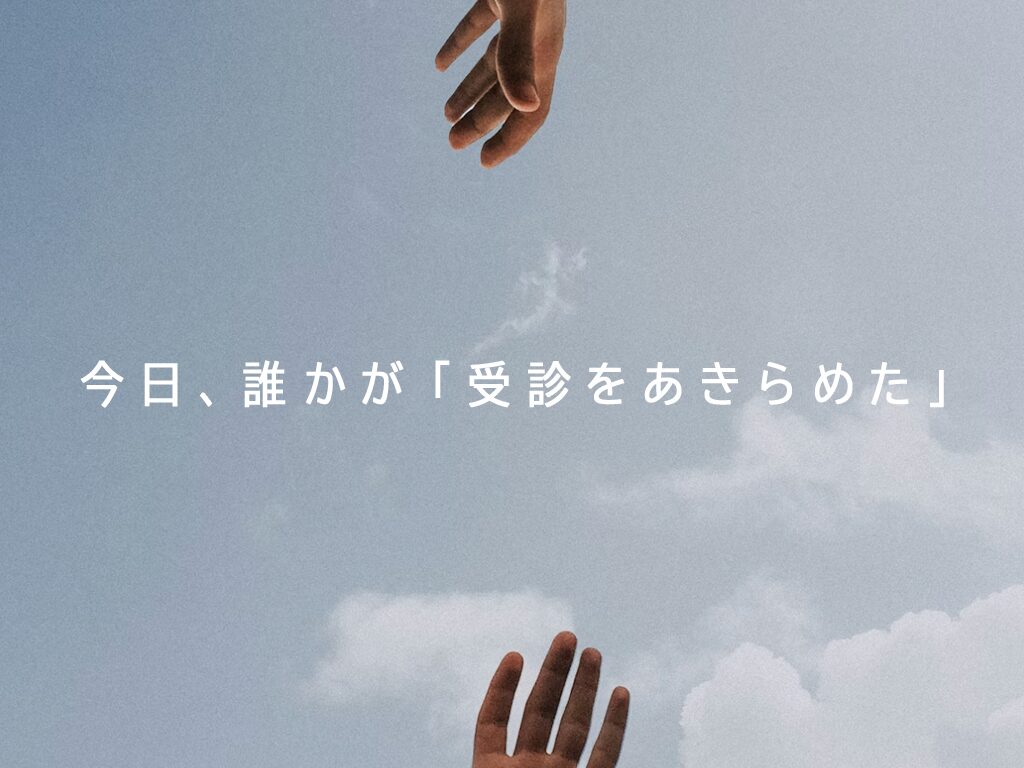山間の集落で暮らす高齢の女性がいました。
腰の痛みが強くなってきても、家から最寄りの病院までは車で50分。
バスは一日3本。冬は雪で道が閉ざされることもある。
「今日は痛いけど、まあ我慢できるからいいか」。
そう言って受診を先延ばしにした結果、彼女は気づいたときには歩けなくなっていた。
これが“医療格差”と聞くと大げさに思えるかもしれませんが、
「受診できるか/できないか」が、人生の質を静かに左右していく。
そんな現実が、日本のあちこちで起きています。
医療格差は、派手なニュースにはなりません。
けれど、確実に暮らしの根っこを揺らしていく問題です。
ここでは、日本の医療格差を「構造」「アクセス」「健康結果(アウトカム)」の3層に分けて、
データと共に “人の生活としての実感” を交えて紐解いていきます。
目次
医療を提供する“土台”の差は、静かに広がっている
医師のいる町と、いない町の「風景の違い」
ある地方の小さな町では、数年前に産科医がいなくなった。
妊婦たちは、片道1時間以上かけて隣県の病院に通う。
冬の雪、夏の交通渋滞、急な陣痛……そのどれもが生活と不安を同時に揺さぶる。
厚労省の統計でも、医師数の地域差は明確です。
都市部の医師数が 人口10万人あたり320〜340人 に対して、
地方やへき地では 175〜200人 ほど。
(約1.5倍の差)
→ これは「診てもらえる可能性」が1.5倍違うという意味に等しい。
この差は、小児科・産科・救急といった
“人生の岐路”に絡む診療科ほど大きい。

医療機関の“灯が消える”ということ
医療は場所に存在するだけで価値がある。
しかし過疎地域では、採算が取れず病院や診療所が閉じていく。
病院が減るというのは、
「医療サービスが不便になる」程度の話ではありません。
- 急病のときに救急車が間に合わない
- 分娩できる病院がなくなる
- 通院できず慢性疾患が悪化する
つまり「住めるかどうか」の問題に直結します。
医療の“持続可能性”が危うい地域
医師が高齢化し、後継者がいない。
救急受け入れを夜間だけ縮小する。
診療科を二つから一つに絞る。
こうした動きは「縮小」の前兆です。
地域医療は、崩れてからでは間に合わない。
“じわじわと薄まる”ことこそが最大のリスクと言われます。
受診までの距離と時間が、“受けられる医療”を決めてしまう
受診に“1時間必要な日常”とは?
都市部では徒歩5分のクリニックでも、
地方では次のような現実があります。
- バスは1日3〜4本
- 車がないと通えない
- 片道40〜90分が当たり前
- 冬は道路が閉鎖されることもある
この移動負担は、高齢者・子ども・障害者・妊婦など、
“もっとも医療が必要な人”ほど大きな壁になります。
医療が遠いということは、
「受診を諦める回数が増える」ということ。
小さな我慢が、未来の大きな健康リスクに変わる。
受診控えの連鎖
医療アクセスが悪い地域では、以下の現象が起きます:
- 子どもの定期健診を逃す
- 産婦健診の完遂率が下がる
- がん検診が受けられない
- 薬が切れても通院できず放置する
受診率の差はそのまま、
予防できたはずの病気が防げない
という格差につながります。

健康アウトカムにあらわれる“地域間の人生の差”
予防できたはずの病気が増える
受診のしにくさは、生活習慣病や小児の虫歯、
慢性疾患の悪化として数字に現れます。
都市部と地方で罹患率に差が出るのは、
単に“生活の違い”だけではない。
医療が遠いほど、重症化しやすいからです。
救急の「間に合わなかった」が増える
救急医療の地域差は命に直結します。
- 脳卒中
- 心筋梗塞
- 外傷
- 産科救急
これらは“時間との勝負”の病気ですが、
病院の距離・救急体制が弱い地域ほど、
重症や死亡の割合が増える傾向があります。
「あと10分早ければ助かったかもしれない」
――そんな現実が、数字の裏にあります。
健康寿命の地域差は“人生の質”の格差
日本は世界有数の長寿国ですが、
健康寿命は都道府県ごとに明確な差があります。
健康寿命が短い地域では、
早くから介護が必要になったり、
自立して生活できない期間が長くなります。
つまり、
「どこに住むか」で人生の後半の質が変わる」
という問題が起きているのです。
医療格差は、派手には見えない。だからこそ見続ける必要がある
医療格差は、貧困問題ほど可視化されません。
症状が軽い段階では見えず、
問題が表面化するときには手遅れになっていることすらある。
そして何より危険なのは、
医療格差が“自己責任”の影に隠れてしまうことです。
・交通手段がなく通えない
・病院が閉鎖された
・専門医が地域にいない
・検診を受ける余裕がない
どれも「個人の努力」ではどうにもならない環境要因です。
医療格差は、
その地域で「生きられるかどうか」そのものを左右する問題。
だからこそ、
社会として、自治体として、“公平性”の視点を持ち続ける必要があります。
最後に:静かな格差を、静かなうちに見つける
医療格差は“突然悪化する”のではなく、
“気づかれないまま積み重なる” ことで深刻になります。
今日、誰かが「受診をやめた」
その理由が、
距離、時間、経済、制度の隙間――
そのどれであっても放置すれば格差は拡大します。
医療は社会の基盤であり、
誰もが必要になるものです。
だからこそ、
数字だけでなく、“暮らしの物語”として
医療格差を見つめることが大切です。
小さな気づきを積み重ねることが、
大きな崩壊を防ぐ最初の一歩になります。